
みにきて! みつびし
スポーツを通じ「和を養い和を貴ぶ」養和の精神を子どもたちに伝える
三菱養和会
施設DATA
訪問記を読む
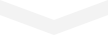

夕方のグラウンドで練習に打ち込む子どもたち。三菱養和会が彼ら・彼女らに伝える「養和の精神」とは?
|
東京都豊島区に建つ「巣鴨スポーツセンター」は、サッカーグラウンドや武道場、50メートルプールに広い体育館などを備えた、都市部にありながら広大な敷地を持つスポーツ施設です。この施設を運営しているのが、公益財団法人三菱養和会。その発祥は、1914年(大正3年)に三菱第三代社長・岩崎久彌を会長として設立された「三菱倶楽部」にさかのぼります。
三菱倶楽部は三菱社員の親睦、体育の向上を目的としていましたが、会社の福利厚生にとどまらず、社員の精神的修養、人格の錬磨も掲げていました。第四代社長・岩崎小彌太は1940年(昭和15年)に三菱倶楽部を財団法人として社業から独立させ、自ら会長に就任。名を「三菱養和会」としました。
その後1974年に戸田艇庫(埼玉県戸田市)、三菱創業百周年の記念事業の一環として、1975年に巣鴨スポーツセンターを開設し、社会体育の振興を事業の柱とした活動を開始。2003年にはスポーツセンター内に武道場「思斉館(しせいかん)」を、東京都調布市に調布グラウンドもオープンし、2011年4月からは公益財団法人として、幅広い年齢層を対象にしたスポーツの普及・振興、健康の維持増進に関する事業や、スポーツクラブの運営といった事業を展開しています。
これらの施設・設備を活かし、三菱養和会はさまざまな競技の指導等を通じて久彌・小彌太の掲げた「精神的修養、人格の錬磨」を実践しています。それを知るべく、サッカースクールと武道スクール剣道塾でお話を伺いました。
「養和の精神」を伝える競技スクール

トップ選手を目指す「選手コース」。入会にはセレクションへの合格が求められ、毎回多くの希望者が集まる。(写真提供:三菱養和会)
|
夕方の巣鴨スポーツスクールのグラウンドを訪れると、ホイッスルと力強くボールを蹴る音が響いていました。サッカー・ジュニアスクールが練習の真っ最中です。
三菱養和会におけるサッカースクール活動の歴史は非常に長く、1975年の巣鴨スポーツセンター開設当初から開講されています。つまり養和会としてのみならず、日本サッカー界においてもパイオニア的存在のスクールで、これまでに多くのプロ選手や日本代表選手がこのグラウンドから誕生しました。
三菱養和会のサッカースクールには、幼児(年中)~小学6年生を対象とした「ジュニアスクール」と、小学4年生~高校3年生が対象の「選手コース」があり、ジュニアスクールは初めてサッカーを始めるお子さんから、他のスクールやクラブチームに所属しながらさらに技術を磨きたい子までが参加し、サッカーを楽しみ、上達することが目的です。
一方の選手コースは、ジュニア(小学4年生~6年生・U-12)、ジュニアユース(中学生・U-15)、ユース(高校生・U-18)として、年間を通じた選手活動を行うコース。入会にはジュニアスクールでのセレクション合格が必要となり、練習試合、合宿、大会、海外遠征など、トップ選手を目指してより本格的な修練を積むことになります。

グラウンドで子どもたちを見つめながら話す秋庭さん。ご自身のキャリアも、このグラウンドから始まった。
|
お話を伺った統括コーチの秋庭武彦さん(日本サッカー協会公認S級コーチ)は、初年(1975年)度のスクールに参加したお一人。もともとサッカーをプレイしていたところへ三菱養和会のスクール開講の話を知り、もっと上達したいと思って入会されたそう。その後、学生時代に当時のコーチから誘われ、アルバイトとして養和会のスクールで教え始めたのが、コーチ人生のスタートだったそうです。
すでにある程度の経験・レベルのある選手コースと異なり、ジュニアスクールはサッカーと初めて出会う子もいます。秋庭さんは、チームスポーツであるサッカーにおいては「みんなで楽しむ」ことがとても大切と考えています。たとえば試合に勝ったとき、技術の良しあしだけでなく、チームの一員として試合に関わったという記憶は、子どもたちにとって大切な財産になります。
「スクールは『誰でも通いやすいこと』を大切にしています。同じ年齢でも技術的な差があったり、性格的に控えめでなかなか前に出られない子がいたりしますが、そういう子にも目を向け、サッカーとの出会いをいい形で贈れたらと考えています」
そんな思いで指導をされるサッカースクールには、今も「精神的修養、人格の錬磨」の精神が息づきます。チームスポーツを通して「和」を養い、子どもの心身の成長を目指しています。
「子どもたちは、まずは健康であることが一番。そのうえで、スポーツを通じて仲間を大切にする、思いやりをもった人になってほしいですね。上手い・強いより、相手の立場に立って考えられる人になってくれたらと思いながら指導にあたっています」

稽古の始めは正座をして神前に礼! すでに道場にはピシリとした空気が。正面の「寂然不動」(じゃくねんふどう)の書は小彌太の筆によるもの。
|
引き続き熱のこもる指導の続くグラウンドを後にして、今度は隣接する武道場「思斉館」にお邪魔しました。こちらの1階道場で、剣道の稽古が行われています。
一礼をして道場に足を踏み入れると、その瞬間から空気が変わりました。板張りの床を裸足の足が滑り、踏み込む音や、「面!」「胴!」と勇ましい声が飛びます。さすがは武道のスクールという凛々しさです。
思斉館で開催されている三菱養和会の武道スクールには、ジュニア向けには剣道・空手・柔道、成人向けには居合道・合気道、さらに短期講習として弓道の各競技のコースがあります。ジュニア向けは小学1年生~中学3年生を対象に、各人のレベルに合わせたグループでの稽古を行っています。

お話を伺った剣道スクール講師の小田部さん(左)、野堀さん(中)、山田さん(右)。お三方とも教士七段の受有者。
|
三菱グループでは、各社の武道愛好家が「三菱武道会」として集まり、思斉館(1階は床張り、2階は畳張りの道場並びに弓道場)で日々鍛錬に励んでいます。ただ日中は道場を使用しない時間帯も多いため、これを活用し、さらに各社現役社員・OB・OGの武道会会員が講師となって、地域への貢献を目指して始まったのが武道スクールです。
現在指導に当たられている皆さんも、先輩からのお誘いを受けて今に至ります。
「三菱のOBとして恩返しの気持ちで、講師を受け継ぎました」(野堀猛さん)
「受け継ぐにあたって先輩に言われた『上手くできる子もいればできない子もいるが、同じ眼差しをもって指導することが大切』という言葉を、今も講師として大切にしています」(山田信弘さん)

レベル分けはあるものの稽古は基本的に全員一緒に行われ、自然と上級生と下級生のつながりもできていく。
|
山田さんが受け継いだ言葉のとおり、養和会の剣道スクールは勝つことよりも所作や基本を身に付けることに重きを置いているそうです。実際、子どもたちを見ていると、まだ稽古の合間には道場を走り回ってしまうような低学年の子も、道場を出るときは忘れずにぴしっと一礼をしていきます。
「一回の稽古は一時間半。低学年の子はどうしても途中で飽きてしまったりもしますが、子どもたちにもわかりやすい例え話をするなど工夫をして、武道の精神を伝えたいと思っています」(小田部裕さん)
そんな講師の思いは、子どもたちにはしっかりと伝わっているようです。
「年少の子が防具をつけるのを上級生が手伝ったり、更衣室を整理整頓して使うようになったり、助け合いの心や礼儀なども自然と学んでいきます。剣道を学ぶことで、協調性とマナーを身に付けた大人になってくれたら嬉しいですね」(野堀さん)
サッカースクールと同じように、ここでも「精神的修養、人格の錬磨」が指導の根底に受け継がれていることを感じました。
スポーツを通じた人間的成長を目指して

人工芝グラウンドもある巣鴨のグラウンド。
|
ジュニア向けのサッカーと剣道、両スクールの指導者からお話をうかがい、共通して感じたことは「競技を通じた人間的成長」に指導の重点を置いているという点でした。もちろん、技術の上達やそれによる昇級、上位クラスへの合格なども、子どもたちの成長へとつながるものですが、それ以前に、一人の人間として立派な人格や振る舞いを身に付けること、その入り口としてのスポーツという考えが、どの指導者の方にも根付いていると思いました。
各競技に取り組んでもらうにあたって三菱養和会は設備面も充実させており、例えば思斉館の1階道場では床材に足の滑りがよい「霧島松」を使用し、「剣道場として大変すばらしい環境」(野堀さん)が整っています。空調・防音対策も備えられ、防具を道場に置いておくこともできる通いやすさも魅力です。
グラウンドは1975年の設立当初から人工芝(三菱養和会は日本でも初期に人工芝を採用!)で整備され、随時張り替えも行われて常に最適な状態でトレーニングができることが大きなメリットです。調布のグラウンドと2面を有しているため、20チーム参加規模の大きな大会が開催できることも強み。「三菱養和会のこの設備はサッカー競技の普及に貢献しています。ここでスポーツ事業に携われることを、指導者として誇りに思っています」と秋庭さんは話してくれました。
サッカーでは仲間に対する思いやり、剣道では上級生と下級生の助け合いのお話をそれぞれ聞くことができました。三菱養和会を創設した岩崎小彌太は、設立に寄せて記した文章の冒頭に、「和を養い和を貴ぶは三菱所属社員の伝統的精神なり」と書いています。三菱所属社員から地域・社会へと広げられた三菱養和会は、この養和の精神を、今もさまざまな競技を通じ、広く多くの人たちへと伝えています。
タグを選択すると同じカテゴリの他の施設が探せます。


こんにちは! 事務局のカラットです。三菱グループでは文化・芸術・教育などさまざまな分野で社会に向けた活動を行っています。スポーツもそのひとつで、スポーツの普及や振興、技能の向上、スポーツを通じた人材育成にも取り組んでいます。なぜ三菱グループがスポーツを通じた社会貢献活動を行っているのでしょうか? 今回は三菱養和会におじゃまし、その歴史を紐解きながら、現在に受け継がれる「養和の精神」についてお聞きしてきました!