新入社員時代はボート・ラグビー・サッカーをかけ持ち!
取引先に愚直に向き合う「営業マン精神」こそ私の真骨頂
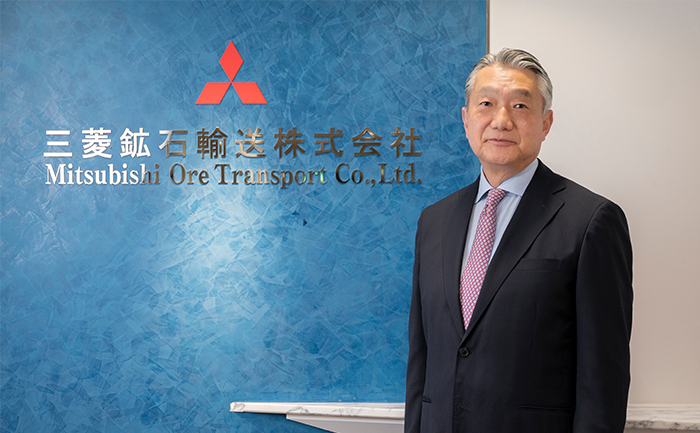
ペットは保護犬だった3歳のコムギ(雑種)。メスだと言われたが、引き取った後にオスであることが判明した。「毎朝私を起こしに来るので一緒に散歩に行く。癒やされる存在です」
三菱鉱石輸送 代表取締役社長
小笠原 和夫(おがさわら・かずお)
1958年生まれ。1982年に慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本郵船に入社。コンテナ船、自動車船部門でキャリアを形成。海外駐在のあと、広報、IT部門の責任者を歴任。製鉄原料グループ長、経営委員(現執行役員)を経て2013年に取締役・経営委員に就任。その後、取締役・常務経営委員、常務経営委員となる。2018年6月に三菱鉱石輸送に転じて代表取締役副社長に。2021年6月より現職。
三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第7回は三菱鉱石輸送の小笠原 和夫社長に、新入社員や若手社員時代の心に残る出来事や、日本郵船の子会社としてリスタートした同社の今後の展開などを聞いた。
――小笠原社長は親会社の日本郵船のご出身です。どんな会社員生活を送られたのでしょうか? 入社した頃のお話からお伺いしてもよろしいですか?
小笠原小学校からサッカーを始めて、中学、高校の頃までは結構真面目に取り組んでいました。大学では同好会でプレーを続けました。ですから、入社後も海運リーグ(海運会社によるリーグ戦)に出場したりしていました。入社後の2年間はそれに加えてラグビーもしていたんですよ。のちに日本郵船で社長、会長になり、政府の規制改革・民間開放推進会議議長や経団連副会長も務めた草刈 隆郎さんが当時の採用担当でした。草刈さんは都立日比谷高校のラグビー部出身で、日本郵船のラグビー部にも関わっていらしたわけです。内定者懇親会の時に私を含めて体育会系の新入社員5人が集められ、「来週、ラグビーができる支度をして会社のグラウンドに来い」と言い渡されました。入社前年の11月ですよ。しぶしぶ出向いたら、いきなり「タックルしろ」と言われて(笑)。それから入社直前の3月まで毎週土日はグラウンドに通い、OB戦に出場したりしました。その時、ラグビー部の2年先輩だったのが、日本郵船の長澤 仁志会長です。
―――新入社員時代の方が、学生時代以上に体育会系の生活だったわけですね。
小笠原確かに体育会系的な会社でしたね。入社直後はボートも漕ぎましたからね。私が配属された東京支店の当時の支店長が、ボート競技(かじ付きフォア)で1952年のヘルシンキ五輪に出場された武内 利弥さんだったんです。辞令をもらって武内さんのところにあいさつに行ったら、いきなり「君、ボート漕ぐか?」と聞かれました。日本郵船では年1回部対抗で水上運動会を開催していて、ボート要員を探していたんです。その年は5月末の開催で、1週間の新入社員研修を終えて配属された翌週から、25日間の合宿に参加しました。埼玉県戸田市にボートの練習場があり、月曜・水曜・金曜・土曜日は戸田に泊まり込みです。ウィークデイは17時の終業と同時に支店を出て戸田に行って2時間漕いで、翌朝は5時に起床して2時間漕いでから出社。クルーを組んでいたのがサッカー部の仲間だったので、土日も朝夕はボートを漕いで、昼間だけ会社のグラウンドに行ってサッカーの練習や試合に汗を流すという、今思えば相当なハードな毎日でした。

――新人時代だと、仕事でもたくさん覚えることがあって大変だったのではありませんか?
小笠原普通に業務をこなしていましたよ。確かに肉体的にはきつかったですが、今となってはいい思い出です。もともと日本郵船は家族的な社風で、運動部の活動が盛んだったり、社内のイベントが多かったりします。当時は社内全体がおおらかで、「仕事は楽しくやらなきゃ」という雰囲気もありました。
大型案件のキャンセルで学んだ営業マンの心得
――若手社員時代のお仕事で印象に残っているエピソードもお聞かせください。
小笠原入社後はコンテナ船部門に9年、自動車船部門に10年在籍しました。強く印象に残っているのは、自動車船部門時代の出来事ですね。中南米航路を担当していた頃、自動車専用船が足りず、バナナや冷凍の肉や魚を運ぶ冷凍船に自動車を積んで運搬していたことがありました。ある商社からジャマイカのキングストン港に250台運んでほしいという要請があり、冷凍船チームに頼んで1隻押さえていました。すると、船積みの3日前にいきなり全量キャンセルになってしまったんです。当時の冷凍船チームの課長が長澤会長で、どなり飛ばされるのではないかと恐る恐る電話で報告したら、「それ、本当にキャンセルなんだな?ないんだな?」と意外にあっさりした反応で、拍子抜けしました。あとで分かったのですが、長澤会長の立場では私のことをどなりつけるより、一刻も早く、その船を他のビジネスに振り向けることの方が重要だったのでしょう。その電話のあと、商社にキャンセル料をもらいに行こうとしたら、当時の上司だった課長から「お前、どこ行くんだ?」と声をかけられました。それまでの経緯を話して「キャンセル料、請求してきます」と出かけようとしたら、課長がポツリと「俺だったら請求しないけどな」とつぶやいたんです。
――聞き捨てならない課長のひと言、それを受けて小笠原社長はどうされたのですか?
小笠原最初は「何言ってるんだよ」と思いました。ホテルにたとえるなら宿泊の3日前に250人の団体客がキャンセルになったくらいの話ですから、キャンセル料をいただくのは当然と考えていました。しかし、先方に伺って来客用の椅子に座った途端、なぜか「キャンセル料はいただかなくて結構です」という言葉が口をついて出てきたんです。先方はもう大喜びでした。これもあとで知ったことですが、担当していたのは商社の運輸部で、船を手配することで営業部門から仲介手数料を受け取ってはいなかった。ですから、キャンセル料を請求されたらそもそも払う原資がないと気が気でなかったようです。おかげで向こう1年間、運輸部が差配する中南米航路の案件はすべて日本郵船にお声がけいただくことができました。仕事とはこういうものなのかと考える契機になった、実に印象的な出来事でしたね。
――この出来事が、その後の小笠原社長のビジネスパーソンとしての姿勢に大きな影響を与えたわけですね?
小笠原私は営業部門が長かったこともあり、取引先が何をしてあげると一番助かるのか、逆に何をされると困るのか、時間をかけて寄り添いながら少しずつ引き出していくことが重要だと考えるようになりました。ですから、「愚直」や「一生懸命」という言葉を座右の銘に、いろいろなお客様と接してきました。難しいお客様でも愚直に向き合っているうちに心が通じ合い、長いお付き合いになったことも少なくありません。最近はリモートワークが進んでいますが、私の経験では、社内や取引先で直に相手の顔を見て、その表情から学ぶことは多いと思います。

1996年38歳、駐在先のロンドン。自宅から約100mの距離にテニスの聖地ウィンブルドンがあった
部長と取っ組み合いのけんかをしかけたことも
――自分だったらキャンセル料を請求しないとおっしゃった課長のような上司から学ぶことも多かったのですか?
小笠原仕事をしていく上で上司や先輩社員に救われたことは数え切れないほどあります。自動車船部門時代には、こんな経験もしました。当時はかなり円高が進行しており、チリの取引先から「輸入車自体の価格が高騰していて、運賃を払うと商売が成り立たなくなる」と泣きつかれ、3割近い運賃の値下げを決めたんです。当時は課長代理でしたが、もちろん独断で決めたわけではなく、上司の課長とファクスでやり取りしていました。当時の課長が、後に社長、会長を務めた工藤 泰三さんです。しかし、帰国後、担当部長が烈火のごとく怒り、「こんな大きな値下げを勝手に決めやがって」と言ってきました。その時は工藤さんが「小笠原もいろいろ考え抜いた末のことですから」と間に入って収めてくれました。しかし、それだけでは終わらなかったんです。部長や工藤さんと一緒に取引先を接待したあとに飲み直していた際、部長が「お前なんか会社辞めろ」と絡んできて、あやうく取っ組み合いのけんかになるところでした。その時も工藤さんが身を挺して「部長、こう見えても小笠原にはいいところがたくさんあるんです!」と必死で止めてくれました。まぁ、部長も部長で、翌日になると「昨日はちょっと飲み過ぎたかな」という程度でその後も一切根に持つことはなかったんですが(笑)。

――昭和の言葉で言うなら「バンカラ」な社風なのですね。小笠原社長はそんな日本郵船に36年間勤務したあとに三菱鉱石輸送に移られたわけですが、三菱鉱石輸送にはどんな印象をお持ちですか?
小笠原日本郵船が船を使ってビジネスを行う「オペレーター」であるのに対し、当社は自身が船舶を保有する「オーナー」です。私が日本郵船の製鉄原料グループにいた頃は良きパートナーでした。個性的な先輩がたくさんいらして「うちの船使ってよ」「今度ゴルフに行こうよ」と頻繁に声がかかったものです。しかし、私が入社した時にはそうした方々は退任され、すっかりイメージが変わっていました。今の日本郵船は大半が陸上社員ですが、当社は半数が海上籍です。安全運航第一で、とにかく真面目で実直な社員が多い。それはそれで素晴らしいことだと思います。反面、「先輩から言われたことをしっかり守っていく」だけの社風は変えていく必要があります。ただ受け入れるのではなく疑問に思う、自分がどうしたいのか考える、アプローチを変えて業務を効率化するといった改革を今進めているところです。当社に来て5年が経ち、それがじわじわ浸透してきたという手応えは得ています。
外国人船員再契約96%の「愛される理由」
――御社はフィリピンにマンニング会社をお持ちで、自社の船にはその会社から船員を配乗していると伺いました。都度契約だそうですが、驚いたのは船員の方が休暇後に再契約して戻って来る割合が96%と極めて高いことです。なぜだと思われますか?
小笠原初めは当社の業務が楽だから皆戻って来るのかなと思っていたのですが、そうでもなさそうです(笑)。社員が40人強という小さな会社ならではの家族的な雰囲気が好感を持たれているのではないでしょうか。東京のオフィスにいる社員なら、今この船に乗っているのは船長が誰々で機関長が誰々……と、すぐに顔が思い浮かびます。加えて、東京のオフィスにも7人のフィリピン人スタッフがいて直接船とやり取りしているので、船からのリクエストはすぐに届きますし、逆に本社が考えていることも船員に伝わりやすいんです。私自身も船が日本に寄港する度に足を運び、その都度、今の会社の状況、船員の仕事やお客様のリクエストに応じることの重要性などを丁寧に説明するようにしています。そうすると彼らも納得して、「頑張ります」とか「それなら、ここを変えてほしい」といった反応も出てくるようになりました。
――風通しのいい職場環境が醸成されているのですね。そうした中で今年4月、御社は大株主だった日本郵船の完全子会社になりました。それによって、何が、どう変わるとお考えですか? 子会社としてどんな役割を果たしていきたいですか?
小笠原例えば新しい船を発注しようという時、これまでの取締役は出身母体が違うので意見の調整が難航したこともありました。しかし、日本郵船は同じ船会社同士で考えが近く、やりやすい面はあります。一方で、以前一緒に働いていた仲間にはこちらの手の内が分かっているので迂闊な真似はできません。ただ、日本郵船と当社は同じ船会社でも業務内容が違いますから、棲み分けはきっちりできているように思います。日本郵船がこれまでの経緯などからお付き合いしづらいお客様とつながりを持ち、NYKグループとしての商圏を拡大していくのも当社に求められる役割のひとつと考えています。さらに、LNG(液化天然ガス)燃料などの新しい技術に関しても、まずは小回りの利く当社でやってみて、お客様に展開する際にどこが課題になるかを見極めるといったリトマス試験紙的な使い方をしてみるのがいいんじゃないですかと、日本郵船の曽我 孝也社長にはお伝えしました。
――日本郵船の曽我社長とはお互いグルメで時に食事をともにされることもある仲と伺いました。
小笠原私自身、食にはこだわる方だと思います。世界各国でいろいろな料理を口にしてきましたが、一番おいしいと思ったのはアルゼンチンに何度か出張した際、ブエノスアイレスで食べたステーキです。市内のラプラタ川沿いにステーキ店がぎっしり並んでいるんです。新鮮な肉を豪快に炭火で焼き上げたステーキは、濃厚なメンドーサワインの赤と実によく合います。日本郵船でも屈指のグルメのつもりでしたが、唯一敵わないと思ったのが曽我社長です。曽我社長も肉好きですね。お酒も強く、二人で夕食に日本酒2升を空けたこともあります。その時私が飲んだのはせいぜい8合くらいでしたよ(笑)。
グループの壮大なプロジェクトから生まれた会社
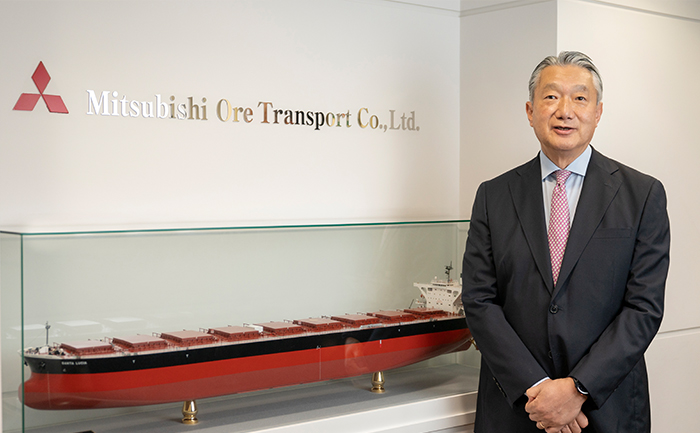
――それは日本郵船とのシナジーにも期待できそうですね。最後に、『マンスリーみつびし』の読者へのメッセージをお願いします。
小笠原当社は終戦後、禁輸措置により日本がオーストラリアなどの主要生産国から鉄鉱石を買えなかった時代に八幡製鉄所(現日本製鉄)の要請を受けて三菱商事と三菱鉱業(現三菱マテリアル)がチリで鉱山を開発し、三菱造船(現三菱重工)がそれを日本に輸送するための船を造って三菱海運が運航するという三菱グループによる壮大なプロジェクトの中で、その船を保有する会社を作ろうと生まれた会社です。創業時の社名は「千代田鉱石輸送」でした。しかし、1964年の海運業界の6グループへの集約で三菱海運が日本郵船の傘下に入り、三菱を冠する船舶会社がなくなってしまうことへの危機感から「三菱鉱石輸送」に社名を変更したんです。
創業時から会社の使命は変わってきていますが、日本の国益にとって大変重要な海上輸送の役割を、三菱グループの中で担い続けています。
当社の社員を含め、三菱グループの皆さんに対してお伝えしたいのは、グループの誇りを胸に常に未来志向で仕事に取り組んでほしいということです。職務を全うすることで社会に貢献しているんだという誇りを持ち、楽しみながら、時には過去から伝わる仕事のスタイルに疑問をはさみつつ、よりよいやり方を追求していっていただけたらと思います。