
三菱と横浜の「縁」(えん・ゆかり)
横浜の玄関であり、憩いの場でありたい
-三菱倉庫-
横浜の各地を訪問し、三菱グループと横浜が織りなす縁(えん/ゆかり)を紹介するこのシリーズ。第3弾は、100年以上にわたって物流のパイオニアとして経済を支え、ロジスティクスに革新を起こしてきた三菱倉庫を取材しました。「いつもを支える。いつかに挑む。」をパーパスとして掲げる同社は、倉庫と物流、そして不動産事業を通じて横浜とどう関わってきたのでしょう。南本牧第一営業所の所長・森田亨さん、横浜ベイクォーターを運営する横浜ダイヤビルマネジメント株式会社の代表取締役社長・福井健夫さんにお話をお伺いしました。
横浜の港からインフラを支えるパイオニア

空から見た南本牧ふ頭≪写真提供:横浜川崎国際港湾(株)≫
|
三菱倉庫は、1880年に開業した三菱為換店の倉庫業務を継承し、1887年に有限責任東京倉庫会社として東京・深川で創業しました。深川での創業後、大阪・神戸の主要港に事業範囲を拡大し、横浜に進出したのは1913年。当時の運送手段は艀(はしけ)や蒸気船が中心でしたが、それから在来船やコンテナ船と扱う船が大型化していきます。三菱倉庫は横浜港のターミナル運営や船舶への貨物の積み込み、さらに「本船荷役」(港湾における船舶への貨物の積み込みや船舶からの貨物の取り下ろし作業)の効率的で正確な荷役業務などで信頼を得ながら扱い高を増やし、大きな存在感を示し続けてきました。
戦後、1968年には倉庫で利用していた土地にオフィスビルを建てるなど、不動産事業にも進出。現在も横浜地区では「横浜ベイクォーター」や「横浜ダイヤビルディング」などの商業施設、オフィスビルを運営しています。
戦後、1968年には倉庫で利用していた土地にオフィスビルを建てるなど、不動産事業にも進出。現在も横浜地区では「横浜ベイクォーター」や「横浜ダイヤビルディング」などの商業施設、オフィスビルを運営しています。
横浜港とともに発展し続ける三菱倉庫

|
社名の由来にもなっている倉庫事業では、1914年に輸入綿花の荷捌場所として表高島町(現在の金港町付近) にあった施設を買収しました。その後、海上業務の拠点として海岸通に「横浜出張所」を、陸上業務の拠点として高島町に「神奈川出張所」を建設。倉庫業務を拡大していきます。1923年、関東大震災での被災もありましたが、1929年に海岸通に海岸通A号倉庫を、隣接してB号倉庫・支店事務所を建設。当時の三菱倉庫 事務所棟は横浜税関・日本郵船横浜支店と一緒に海岸通沿いに並び、美しい建築デザインで景観を作りあげていました。1988年に神奈川県の要請により当地を売却し、神奈川警察本部庁舎が建てられましたが、今でも庁舎の前庭に三菱倉庫が所在したことを示すプレートが残っています。
海岸通の倉庫はなくなりましたが、後に建てられた大黒ふ頭や南本牧ふ頭の倉庫は現在も横浜港湾地区の物流拠点として活躍しています。特に、南本牧ふ頭の南本牧配送センターは、最新のシステムが導入された物流拠点で、食品や原材料の輸出貨物などを取り扱っています。ふ頭内にある国内最大の水深岸壁(-18m)のコンテナターミナル 「MC-3/4」は首都圏各地へのアクセスも良いことから、多様な物流状況に対応しています。
海岸通の倉庫はなくなりましたが、後に建てられた大黒ふ頭や南本牧ふ頭の倉庫は現在も横浜港湾地区の物流拠点として活躍しています。特に、南本牧ふ頭の南本牧配送センターは、最新のシステムが導入された物流拠点で、食品や原材料の輸出貨物などを取り扱っています。ふ頭内にある国内最大の水深岸壁(-18m)のコンテナターミナル 「MC-3/4」は首都圏各地へのアクセスも良いことから、多様な物流状況に対応しています。

神奈川警察本部庁舎前にある、三菱倉庫跡地のプレート
|

当時、モダンな建築デザインで有名だった横浜支店
|

最先端の設備が整う南本牧配送センター
|
物流は時代を映す鏡
横浜進出当初の横浜駅周辺から本牧方面へと、横浜港の拡大と荷扱量の増加に対応するため拠点が変わっていったように、取扱品目も時代とともに変わりました。戦中は軍需産業の原料が多かったのですが、戦後は生活物資の取扱が再開。港湾荷役では、米国からの救援物資(小麦・缶詰等)や、軍貨の船内荷役業務を開始しました。戦後はまさに港・倉庫の両輪で「衣」「食」「住」を支え、復興の一助となったといえます。その後も、高度経済成長期、バブル期、そして平成、令和と、時代を映すように取扱品目は変化し続けます。コロナ禍当初は、荷の扱いが大きく減少しました。また、特定の産地の農作物の扱いが増えたり、逆に減ったりするのを見ると、「これが最近は需要があるのか」「このあたりでは不作が続いているのか」と、まさに水際で感じることもあるそうです。
横浜港とは、海と魚の関係

南本牧第一営業所所長・森田亨さん
|
1965年、アメリカからコンテナリゼーション(コンテナによりユニット化された貨物のDoor to Doorの一貫輸送システム)がもたらされると、三菱倉庫もターミナルの運営・コンテナの陸上輸送・コンテナの混載輸送・フォワーディング業務(荷主から貨物を預かり、輸出入の輸送に関わる船舶の手配から荷受人への納品までの業務)など付帯するさまざまな業務への進出を急ピッチで進めます。1978年には、横浜港の本牧ふ頭(D突堤)で、コンテナターミナルの運営を開始。その後、大黒ふ頭・南本牧ふ頭とターミナル業務を拡大していきます。
ターミナル業務で最も大切なのは、安全を前提とした効率と正確さです。2012年には南本牧MC-1/2ターミナルが、荷役効率(1時間あたりのコンテナ積み込み本数)で世界1位を獲得しました。コンテナの積み込みは、通常1時間あたり20本程度が平均ですが、長年培ってきた現場でのノウハウがしっかりと引き継がれ、作業会社とのチームワークも良好、更には最先端のシステムが導入されている南本牧では35~45本を積み込みます。荷役が早く終わると、船も余裕をもって出港できるため、より安全な航海が可能になります。
ターミナル業務で最も大切なのは、安全を前提とした効率と正確さです。2012年には南本牧MC-1/2ターミナルが、荷役効率(1時間あたりのコンテナ積み込み本数)で世界1位を獲得しました。コンテナの積み込みは、通常1時間あたり20本程度が平均ですが、長年培ってきた現場でのノウハウがしっかりと引き継がれ、作業会社とのチームワークも良好、更には最先端のシステムが導入されている南本牧では35~45本を積み込みます。荷役が早く終わると、船も余裕をもって出港できるため、より安全な航海が可能になります。

国内最大の水深岸壁(-18m)のコンテナターミナル 「MC-3/4」
|

広い車両待機スペースを備え、スムーズな搬出入を実現
|

システム化されたゲート
|
アート&デザインの街づくりを体現
横浜の新名所としてすっかり定着した「横浜ベイクォーター」は、横浜駅東口エリアの金港町に建っています。この場所は、三菱倉庫が1914年に横浜進出の第一歩を踏み出した思い入れのある土地です。三菱倉庫は、この金港町で約70年もの間、横浜港の拠点として倉庫業を営んだのち、1985年に隣にオープンした「そごう横浜店」にあわせて倉庫跡地で平面駐車場を営みます。そして2004年に横浜駅の「きた東口」から続くヨコハマポートサイド地区の再開発がスタートすると、2006年にこの土地にショッピングモールとして横浜ベイクォーターをオープンさせました。
ヨコハマポートサイド地区の開発コンセプトは「アート&デザインの街」。港に停泊する白亜の豪華客船のような外観は、まさにそのコンセプトを体現するような美しいデザインです。
横浜ベイクォーターに入ってまず驚くのが、その開放感です。個性的な飲食店やショップは、海に向かってテラス席が設けられ、中央の広場は、イベントや憩いの場として活用されています。2階には「シーバス」乗り場(横浜駅東口のりば)が併設され、山下公園や赤レンガ倉庫、横浜ハンマーヘッド(新港ふ頭桟橋)との行き来ができ、文字通り横浜観光の玄関口となっています。
ヨコハマポートサイド地区の開発コンセプトは「アート&デザインの街」。港に停泊する白亜の豪華客船のような外観は、まさにそのコンセプトを体現するような美しいデザインです。
横浜ベイクォーターに入ってまず驚くのが、その開放感です。個性的な飲食店やショップは、海に向かってテラス席が設けられ、中央の広場は、イベントや憩いの場として活用されています。2階には「シーバス」乗り場(横浜駅東口のりば)が併設され、山下公園や赤レンガ倉庫、横浜ハンマーヘッド(新港ふ頭桟橋)との行き来ができ、文字通り横浜観光の玄関口となっています。
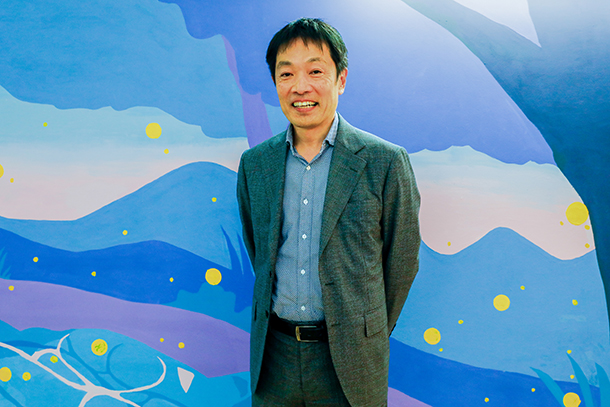
横浜ダイヤビルマネジメント株式会社代表取締役社長・福井健夫さん
|

船のような外観の横浜ベイクォーター
|
地元で愛されるまでの道のり

開放感ある横浜ベイクォーターのテラス席
|
今では、地元の方々の憩いの場として、そして横浜観光の新名所として親しまれている横浜ベイクォーターですが、ここまでの道のりは、平坦ではありませんでした。
ヨコハマポートサイド地区は、もともと倉庫や工場などがあった工業地帯。オープンしたばかりの頃は、認知度が高くありませんでした。そこで、愛犬のお散歩ついでに寄ってもらえるように、ペット連れOKの施設をアピールし、ドッグコンテストのようなイベントも開催しました。今でこそ、愛犬同伴可の施設は珍しくありませんが、当時はこれほど大きな商業施設でペットを連れてこられる場所は珍しく、大いに話題になりました。
次の問題は、駅からの動線です。オープン当初は、横浜駅のきた東口から横浜ベイクォーターまでの道のりがわかりにくかったため、そごう横浜店の中を通るルートが一番近道でした。そごう横浜店はそのことを知ると、なんと横浜ベイクォーターのサインを店内に設置してくれたのです。横浜で商売を営む会社には、横浜が大好きな人が多く、一緒に地元を盛り上げたいという気持ちがあったのでしょう。
ヨコハマポートサイド地区は、もともと倉庫や工場などがあった工業地帯。オープンしたばかりの頃は、認知度が高くありませんでした。そこで、愛犬のお散歩ついでに寄ってもらえるように、ペット連れOKの施設をアピールし、ドッグコンテストのようなイベントも開催しました。今でこそ、愛犬同伴可の施設は珍しくありませんが、当時はこれほど大きな商業施設でペットを連れてこられる場所は珍しく、大いに話題になりました。
次の問題は、駅からの動線です。オープン当初は、横浜駅のきた東口から横浜ベイクォーターまでの道のりがわかりにくかったため、そごう横浜店の中を通るルートが一番近道でした。そごう横浜店はそのことを知ると、なんと横浜ベイクォーターのサインを店内に設置してくれたのです。横浜で商売を営む会社には、横浜が大好きな人が多く、一緒に地元を盛り上げたいという気持ちがあったのでしょう。
こうして、少しずつ地元に浸透していった横浜ベイクォーターに転機が訪れたのは2009年。横浜ダイヤビルディングが竣工するのに合わせて、横浜駅きた通路方面から横浜ベイクォーターに直結する「ベイクォーターウォーク」が開通したのです。文字通り横浜駅と繋がった横浜ベイクォーターは、アクセスが格段に良くなり、横浜の新名所として定着するようになりました。
横浜を盛り上げる「おとなりゾート。」へ

夜の横浜ベイクォーター
|
ベイクォーターウォークの開通以来、多くのお客さまに来ていただけるようになった横浜ベイクォーターですが、休業を余儀なくされた時期があります。2020年~の緊急事態宣言期間です。コロナによる緊急事態宣言が長引いた頃、もちろん店舗は休業していましたが、施設のデッキの一部を開放していました。横浜ベイクォーターには、いつも愛犬のお散歩コースとして寄ってくださるお客様が何人もいて、その方々に、少しでもいつも通りの解放感を味わってもらいたいという想いからでした。そのときに、お客さまから寄せられた「横浜ベイクォーターがあってよかった」という言葉は、今も多くの社員の心に残っています。
開業以来、ずっと大切にしてきたのは、地元・横浜の人々に愛される公園のような場所でありたいということ。横浜ベイクォーターの中にある神奈川大学美術部の描いた大きな壁画を見て、壁画を描くために神奈川大学の美術部に入ったという人もいたそうです。横浜ベイクォーターの結婚式場で結婚式を見てから、この場所で結婚式を挙げるのが夢と話す人もいます。子どもの頃から慣れ親しんだ横浜ベイクォーターが大好きで、運営会社の横浜ダイヤビルマネジメント株式会社に入社した社員もいます。オープン当初は手探りだった横浜ベイクォーターは、今では地元に馴染み、横浜にとってなくてはならないものになりました。
開業以来、ずっと大切にしてきたのは、地元・横浜の人々に愛される公園のような場所でありたいということ。横浜ベイクォーターの中にある神奈川大学美術部の描いた大きな壁画を見て、壁画を描くために神奈川大学の美術部に入ったという人もいたそうです。横浜ベイクォーターの結婚式場で結婚式を見てから、この場所で結婚式を挙げるのが夢と話す人もいます。子どもの頃から慣れ親しんだ横浜ベイクォーターが大好きで、運営会社の横浜ダイヤビルマネジメント株式会社に入社した社員もいます。オープン当初は手探りだった横浜ベイクォーターは、今では地元に馴染み、横浜にとってなくてはならないものになりました。

地元の学生が制作した壁画の前にいる社長の福井さん(右)と営業の田中さん(左)
|
2024年8月24日、開業18周年を迎えた横浜ベイクォーターは、施設コンセプトを「おとなりゾート。」としました。コンセプト設定にあたって半年かけて社員で話し合ったところ、18年間、大切に守ってきたことは「地元・横浜の人たちにとって、安心してくつろげるかけがえのない場所でありたい」という想いだという声が多く聞かれました。「おとなりゾート。」には、お客さまの日常の「おとなり」にある、「おとな」が大切な人たちとくつろげるショッピングモールでありたいという想いが込められています。また、四季折々の賑わいを創出するとともに、開放的な環境でリフレッシュできる時間をご提供し、横浜に訪れる人の玄関口として、地元住民の皆さまにとっては公園のような「横浜になくてはならない施設」になるという決意でもあります。
横浜ダイヤビルマネジメント株式会社代表取締役社長・福井健夫さんにとって、横浜とは「海風」だといいます。心が安らぐのと同時に、自由で開放的な気持ちになり、無限の可能性を感じる横浜の海風は、古き良き港町の面影と、未来への期待を同時に抱かせてくれる特別な存在。これからも横浜で働き、街の発展に貢献していきたいと、笑顔で答えてくださいました。
横浜で生まれた笑顔の種は、海風に育てられ、この地で、深く、そして強く根を伸ばします。
横浜ダイヤビルマネジメント株式会社代表取締役社長・福井健夫さんにとって、横浜とは「海風」だといいます。心が安らぐのと同時に、自由で開放的な気持ちになり、無限の可能性を感じる横浜の海風は、古き良き港町の面影と、未来への期待を同時に抱かせてくれる特別な存在。これからも横浜で働き、街の発展に貢献していきたいと、笑顔で答えてくださいました。
横浜で生まれた笑顔の種は、海風に育てられ、この地で、深く、そして強く根を伸ばします。
※2025年1月23日掲載。本記事に記載の情報は掲載当時のものです。