
三菱と横浜の「縁」(えん・ゆかり)
横浜から、エネルギーで暮らしを支える
-ENEOS-
横浜の各地を訪問し、三菱グループと横浜が織りなす縁(えん/ゆかり)を紹介するシリーズ第8弾は、横浜の地から人々の生活を支えるエネルギーを届け続けているENEOSグループのENEOS株式会社を取材しました。同社は事業を通じて横浜とどんな関係を築いてきたのか?
一大拠点であるENEOS 根岸製油所を訪ね、所員の皆さまにお話をお伺いしました。
石油の未来と横浜の未来。託された根岸製油所

細長い敷地は一方は海に、もう一方は公園や住宅地に面している
|
横浜の美しい海と山、住宅地に囲まれた場所に、根岸製油所はあります。首都圏のエネルギー需要を支える重要な拠点として、半世紀以上にわたって操業を続けています。
根岸製油所誕生の発端は、横浜市が掲げた「工業立市」という構想にあります。戦後の復興期を経て、急激に成長へと向かう日本経済のなかで、横浜でも港湾地区を中心とした産業振興の計画が進められていました。そんな構想のもと、工業に適した用地を確保するために根岸湾の埋立計画が発案されたのです。
横浜市が、誘致する重化学工業の企業を検討するなかで、日本石油精製株式会社(現・ENEOS)が候補に挙がりました。折しも同社も横浜への進出を強く希望していたタイミング。「工業立市」を目指す市の熱意と、石油業界の発展を見据える日本石油精製の開拓心がかみ合い、計画は大きく前進します。
当時の副社長の「当社として最大の製油所を建設する」という言葉に表れているように、大きな決意を持って取り組んだ根岸製油所の建設。最先端の設備はもちろん、原油を積んだタンカーが入港できる桟橋など、積み上げてきた技術と情熱をもって建設は進められました。横浜市が埋め立ての計画を行ってから20年あまり、日本石油精製が横浜進出を表明してから5年以上の歳月が流れた1964年。市にとっても同社にとっても悲願の製油所は、まず根岸地区が完成し、その4年後に本牧一地区、さらに4年後に本牧二地区が完成。現在の根岸製油所の姿になりました。
エネルギーを供給し続ける。日常も非日常も支えるプライド

タンカーで運ばれてきた原油は、桟橋からパイプを通って原油タンクへと送り込まれる
|
面積220万㎡、周囲12kmに及ぶ広大な根岸製油所は、国内最大級の規模です。ここでは、タンカーで届けられた原油を受け入れ、ガソリン・灯油・軽油などの人々の暮らしに欠かせないエネルギーに変換し、出荷するまでを行っています。
間近に首都圏という大消費地を控えた立地は、製品供給拠点としては絶好。日々確実にエネルギーを安定供給するために努力を重ねてきました。例えば、点検やメンテナンスの徹底です。パイプやタンクの健全性においても、一つひとつ非破壊検査で状態を確認し補修の計画を立てるなど、細やかな管理がなされています。また、製造装置の定期点検においても地区毎に操業停止が重複しないように計画した上で、設備の点検・補修を行い安全性・信頼性の向上に努めています。このように、不測のリスクに備えながら安定した生産・供給を続けられる体制を常に保つことで操業を継続してきました。その根底には「絶対に供給を止めない」というポリシーがあります。
真価が問われたのは、東日本大震災の時でした。震災直後、根岸製油所では火災などが発生せず、安全に全装置を止めることができました。しかし、装置が停止したままでは、国内向けのエネルギー供給も途絶えるため、安全最優先で動力源を復活させ、社員が一丸となって石油製品の製造・出荷を再開すべく対応に奔走しました。

根岸製油所最大の原油タンク。野球場のグラウンドが入るほどの大きさ
|
同社の仙台製油所が甚大な被害を受けて操業停止に陥る中、被災地への石油製品の供給において根岸製油所は大きな役割を果たしました。被災地からは「根岸から東北の被災地に石油製品を供給してほしい」という要望を受けていました。津波の恐れがあるため船による輸送ができず、高速道路も寸断された状況において、根岸製油所を出発するタンク車による鉄道輸送が命綱であり、日本海側を迂回して被災地まで石油製品を届けました。多くの報道陣が駆けつけた被災後初のタンク車出発の際、社員は涙ながらに見送ったといいます。その後も復興を支えるという強い使命感を持って社員が一致団結し、1年半にわたってタンク車を被災地に送り出し続けました。社会インフラを支えるという使命に対する責任とプライド。長い歴史の中で引き継がれてきた、いかなるときでもエネルギーを供給し続けるというDNAが、危機に瀕する人々の生活を支える力になったのです。
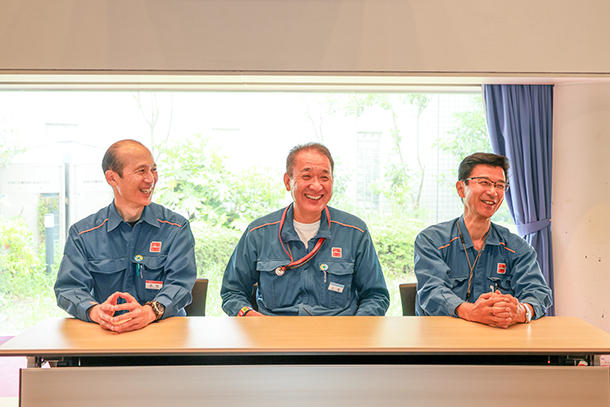
根岸製油所の歴史を知る(左から)大竹 淳さん、三宅 龍志さん、及川 次郎さん
|

鉄道輸送を担うタンク車。敷地内の専用線路から長野県や群馬県などへエネルギーを届ける
|
横浜の人と自然に寄り添う製油所

タンク群の間近に控える自衛消防隊の車両。長さ27mまで伸びるブームは、カメラで状態を確認しながら消火活動ができる
|
根岸製油所は、大型の製油所でありながら隣接するJR根岸線を挟んですぐ向こう側にはマンションや店舗が立ち並ぶ「都市型製油所」です。操業開始以来、市民生活と隣り合わせの製油所として、地域との共生に力を入れてきました。
タンカーからの流出油対策や火災にすぐ対応するための自衛消防隊、消火設備の設置など安全・防災対策を徹底するだけでなく、地域の方々に不安を与えることがないよう、臭いや音も厳しい基準のもとで管理しています。可燃ガスを燃焼させて有害物質を取り除く環境安全装置「フレアスタック」では、噴き出る炎の大きさにまで気を配っています。横浜市の環境条例に基づいて、タンクの色を横浜の海や緑になじむグリーンやホワイト系の色に塗り変えるなど、景観にも配慮しています。地域住民の方から選ばれた「環境モニター」の方に臭いや音の有無を記録・報告していただき、環境管理の改善に役立てる取り組みも行っています。また、近隣の学校の授業に合わせて開催する石油精製や地球温暖化をテーマとした科学環境教室、石油由来のパラフィンを原料とするろうそく作りのワークショップなど、ENEOSならではの地域貢献活動を通じて地域社会との交流を図ってきました。

科学環境教室で地球温暖化について学ぶ子どもたち
|
自然との共生もテーマのひとつ。豊かな自然に囲まれながら操業する中で、環境対策にはいち早く取り組んできました。国の基準よりもさらに厳しい横浜市の基準に則り、大気汚染対策や排水管理を徹底しています。さまざまな環境への取り組みと実績が評価され、1996年に石油業界では世界初となる環境マネジメントシステム「ISO14001」認証を取得。「都市型製油所」として人と自然との共存を実現してきました。
根岸製油所は、根岸湾に面し、周囲を三渓園、本牧山頂公園、根岸森林公園などの緑地に囲まれ、海と山の自然が交差する地域に位置しています。地域の生態系ネットワークの拠点のひとつとなるよう、「工場の中の里山」をコンセプトに、2016年から、敷地内の緑地「中央緑地」を整備して生物多様性の保全活動をスタート。約6万m2もある「中央緑地」では社員と協力会社、専門家が一体となって、生物多様性の保全に取り組んでいます。樹木の伐採、遊歩道の整備、木柵内でヤギに草を食べてもらうエコな除草活動や、ソーラー電源で動く装置による池の水質改善など、着実に取り組みを積み重ねてきました。そうした取り組みが評価され、2023年には環境省「自然共生サイト」に認定されました。現在では、カワセミが飛来し、希少な種のランも確認されるなど、多様な動植物が根付いた生態系が構築されています。
また、この緑地は環境教育の場としても活用されています。横浜市立大学の協力を得て、子ども向けの環境教育プログラムを学生たちと企画。社員とその子どもたちで池の周囲を巡るスタンプラリーをしたり、落ち葉やどんぐりを使った工作をしたり、鳥の巣箱をペンキで彩ったりと、自然と触れ合いながら生物多様性を学べるさまざまな活動を実践してきました。2024年からは地域のご家族を招待するなど、緑地は根岸製油所と地域の人々をつなぐ場所としても成長を続けています。

環境整備を続ける「中央緑地」。地域の生態系ネットワークの拠点を目指す
|

岐阜県からヤギを3頭招いて根岸製油所構内の除草活動を実施
|
地域に根差すENEOS野球部

都市対抗野球大会優勝回数は、最多の12回を誇る
|
ENEOSと横浜とのつながりを語るうえで欠かせない存在が、横浜市に本拠地を置く「ENEOS野球部」です。1950年に「日石CALTEX野球部」として創部され、1956年に都市対抗野球大会で初優勝。以降12回の優勝を重ね、多数のプロ野球選手を輩出するなど社会人野球界の名門として知られています。
「ENEOS野球部」は小中学生・高校生を対象に野球教室を開催し、野球を通じたスポーツの振興、次世代育成に取り組んでいます。2024年度は横浜市内を含め全10回開催し、474名の参加者に、技術にとどまらず野球の魅力を伝えました。
届けるエネルギーは変わっても、社会を支える信念は変わらない

赤い煙突の左下にあるのは現在も稼働する唯一の「常圧蒸留装置」
|
操業開始から60年あまり。根岸製油所は、時代のニーズに応えながら進化し続けてきました。かつてはガソリンや重油、アスファルトなど物流・工業生産を支える燃料の需要は右肩上がりで伸長してきましたが、道路建設の減少や工場の燃料転換、自動車の燃費向上等により国内の石油製品の需要はピークアウトを迎え、特に重油・アスファルト等の重質油の需要は大幅に減少していきました。2022年には、操業当時から稼働を続けてきた根岸製油所の象徴的な設備「第1常圧蒸留装置(トッパー)」はじめ、一部の装置がその役目を終えて停止しました。
そのような目まぐるしい事業環境の変化の中でも、根岸製油所は社会の多様なエネルギーニーズに応えるために、新たな技術に挑戦し続けてきました。一例として、2003年に建設されたIGCC(ガス化複合発電)装置は、余剰の重質油をクリーンなガスへと変換し、発電に再利用することを可能にしました。生み出される電力は、横浜市の一般家庭用電力需要の40%ほど。これはなんと黒部ダムと同程度の発電量に達するといいます。
一大消費地である関東圏に位置する根岸製油所。省エネ等による国内石油製品の需要減少、気候変動対策のための低炭素化の取り組みが進む時代でも、エネルギーの安定供給を通じて地域社会を支えるという信念はそのままに、時代の変化の中で今後どのようなエネルギー供給拠点へと成長を遂げていくのか。根岸製油所のさらなる発展が期待されます。
横浜とともに歩んだ60年

ENEOS 根岸製油所の正門前にて取材調整をしていただいた総務グループの方々
|
根岸製油所を中心に、横浜と深い関わりを築いてきたENEOS。住宅街に隣接する製油所として、市民の理解と信頼に支えられながら、文字通り横浜の自然や人と寄り添うように歴史を重ねてきました。
この横浜の地から送り出された燃料や電力は、無数の家庭や産業の毎日を支え、社会の「今日の当たり前」を支え続けています。時代の変化、エネルギー業界の変化の中でも、ENEOSはエネルギーの安定供給を通じて「明日の当たり前」をリードし、これからも横浜の未来を、日本の未来を支えていくことでしょう。