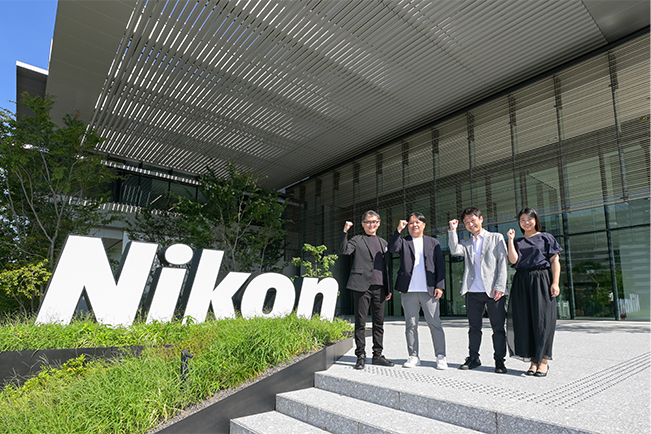
2024年7月、ニコンは本社を東京都港区港南から東京都品川区西大井に移し、新本社ビルでの業務を開始した。西大井は、ニコンが創立した1917年(大正6年)の翌年に工場を設けたゆかりの地。1988年までカメラ製造の拠点となり、その後も一部の部門が稼働し、さまざまな名品を生み出してきた。この原点となる地に構えた本社/イノベーションセンターには、本社地区勤務社員の約3,000人が働く。新本社ビルにこめた思いを、移転プロジェクトチームのまとめ役となった4人に聞いた。
コンセプトは「City of Light」、環境にも配慮
西大井駅からニコンの旧社名・日本光学工業にちなんだ「光学通り」を歩くと、ほどなく大きく直線的なひさしのあるビルが目に飛び込んでくる。「社員一人一人の光でニコンの未来を明るく照らしていきたい」という思いを象徴するひさしは、直射日光を遮りながらも光の反射を利用して建物の奥まで明るく照らすように計算されている。

日射遮蔽効果によって空調用エネルギーを抑制。自然光の利用や自然換気を促す構造、オフィスの稼働状況に応じた可変風量システムの導入などにより大幅な省エネを実現。太陽光発電による創エネを組み合わせ、環境に配慮している。設計は三菱地所設計が担当。
本社移転プロジェクトチームのまとめ役となったのは、計画全体のコントロールを担った鈴木 将史さんと豊田 陽介さん、建築チームの責任者の六日市 清尊さん、事務局として計画進行管理を担当した國嶋 ひとみさんだ。それぞれ自身が所属する部署と兼任という形で、通常業務と並行してこの大規模プロジェクトに携わった。
新本社のコンセプトは「City of Light」。「ニコンは光の可能性に挑んできた会社。光が集まる街のような建物に」という願いが込められている。
コロナ禍での困難を乗り越えたチームメンバー
鈴木さんは新本社ビル建築にあたってキーワードとなった言葉を次のように説明する。
「プロジェクトにおいては3つのキーワードがありました。一つは『シナジー創出』。新本社にはコーポレート部門に加え、カメラや半導体製造装置、顕微鏡など各事業ユニットの企画および先進R&D関連部門を集約することで、事業間のシナジーを生み出す効果を狙いました。二つ目は『コミュニケーション』。社員同士のコミュニケーションを活性化することでエンゲージメント向上も目指しています。三つ目は『環境配慮』。省エネ、創エネはもちろん、地域とも融合し、環境に最大限配慮した建物にしました。これらの大義があったからこそコロナ禍の逆境も乗り越えられたのだと思います」(鈴木さん)

各フロアにはコミュニケーションを生み出す空間をふんだんに設け、部門の垣根を超えた活発な交流を促している。
チームが正式に立ち上がった2021年11月は、コロナ禍の真っ只中。当時はオフィスの存在意義が問われ、計画は一時中断に追い込まれた。また、建設コストの急騰や建設資材の長納期化からくる工程の不透明感など、想定していなかった事象も発生。さまざまな試練が襲いかかったが、だからこそ改めて「どのようなオフィスが社員に求められているのか」を整理して、一致団結した。
柱のない大空間、オフィスでの社員の働き方も変化
6階建て、延べ面積は約4万2,000㎡と広大。3~6階のオフィスフロアは東西に細長い空間となっており、最も長い距離で150m。柱で遮ることのない開放的な作りになっている。この大空間に、多様な働き方に対応した柔軟なワークプレイスを整えた。國嶋さんは語る。
「かつては基本的には固定席でしたが、新本社では部門ごとにエリアを決めてそのエリア内で自由に席を選べる、グループアドレスを取り入れました。また、『コラボレーションエリア』と呼ぶオープンエリアをたくさん設けたほか、ダイニングや屋外のテラスなど、デスク以外の場所でも働くことができるようにすることで、柔軟で魅力的なワークプレイスを実現。新たなコミュニケーションやコラボレーションを生む創造的なオフィス空間を整えました」(國嶋さん)

東海道新幹線が見えるテラスは広々として開放的。さまざまな部門の社員と出会い、会話が弾み、アイデアが生まれる。
プロジェクトメンバーは、図面段階から建物のデザイン、機能、オフィス内のレイアウト、家具什器の選定、食堂のスプーンに至るまで、すべて企画、選定した。豊田さんは語る。
「ここで働く社員だけでなく、各地域の事業所で働く社員も含めたニコン全社員のための新本社。本社を訪れたときには、誰もが同じようにさまざまなエリアを活用して仕事ができるようにしています」(豊田さん)
無意識のうちにまとまったチームワーク
新本社が完成して改めてプロジェクトを振り返り、メンバーは口々に「いいチーム」と称賛し合う。
「メンバーに恵まれました。何百回やったかというくらいたくさん会議を重ねて、効率がよかったかというと必ずしもそうとは言い切れないけれども、それでも乗り越えられたのはこのメンバーだったから」(豊田さん)
「とくに気を使わなくても最初から自然な雰囲気でうまくいきました。2024年度末までこのチームでの活動は続きますが、いつでも居心地がいいチームです」(六日市さん)

フロアを繋ぐ階段にはプロジェクターと腰かけて話せるスペースがある。「自由に使える空間が多い。社員がいろいろな使い方を実践してくれています」(豊田さん)、「光の直進性を表すビルのファサードが最高にかっこいいと気に入っています」(六日市さん)
國嶋さんが「チームのみんながフランクに話し合えていた」と語れば、鈴木さんも「さまざまな困難はあったけれど、あまりポジティブではない情報こそ速やかに共有して、皆で対応を考えようという体制が誰からともなく自然とできていました」と語り、チームの呼吸は最初から最後までぴったりと合っていたことが分かる。
社員から「出社のモチベーションが上がった」との声
8月に社内で行われたオープニングイベントでは、迫力のあるワイドスクリーンと1階と2階をつなぐ大階段を設けたアトリウムに社員が集まった。そのときの社員達の笑顔を見て、メンバーは改めて「設計段階で思い描いていたイメージが具現化され、建築に携わる者として大きなやり甲斐を感じた」(六日市さん)、「当社では初と言っていい自社ビルの本社の建築に携われたことは誇り」(豊田さん)と達成感を味わった。

120席あるアトリウムは新製品発表会など、さまざまなイベントに利用可能。「お客さまがいらしたときに、まず『おおっ』となる大空間。インパクトがあります」(鈴木さん)
アトリウムはニコンミュージアムにつながっている。このスペースは一般来館者も見学可能だ。ふと床を見ると、ところどころがキラキラと光っている。製品基準に至らなかった光学ガラスの廃材を砕いて床材に使っているのだという。こんなところにも「City
of Light」を感じることができる。
「長期にわたり組織全体に影響を与える大規模プロジェクトに関わることができ、貴重な経験や知識を得ることができました。社員から『出社のモチベーションが上がった』などのポジティブなコメントをもらえて、とてもうれしいです」(國嶋さん)

鈴木 将史
MASAHITO SUZUKI
経営管理本部 人材開発部長

豊田 陽介
YOSUKE TOYODA
経営管理本部付 内部統制推進室長

六日市 清尊
KIYOTAKA MUIKAICHI
経営管理本部 工務管理部長

國嶋 ひとみ
HITOMI KUNISHIMA
経営管理本部 人事部 企画課



