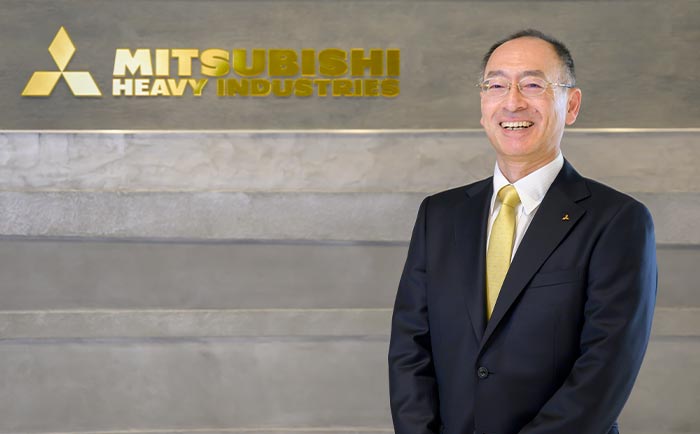三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第27回は三菱UFJ信託銀行社長の窪田博氏に学生時代やキャリアの話、社長としての会社の目標などについて聞いた。

隙間時間を見つけてはジョギングに励む。自分の青春時代である1980年代の洋楽を聴くと活力がみなぎる。好きな食べ物はラーメン。今は気が置けない友人達と居酒屋に行きたい。お酒は何でも飲むが、強くはない。
三菱UFJ信託銀行取締役社長
窪田 博(くぼた・ひろし)
1969年富山県生まれ。1992年東京大学経済学部卒。同年4月三菱信託銀行(現三菱UFJ信託銀行)入社。大蔵省証券局出向、国際業務部、ロンドン支店、経営企画部、営業第1部などを経て、2018年三菱UFJ銀行執行役員営業第一部部長、2019年三菱UFJフィナンシャル・グループ執行役員財務企画部長、2022年三菱UFJ信託銀行常務執行役員営業本部長、2024年取締役専務執行役員(CSO兼CFO兼COO-I)、2025年より取締役社長。
――55歳で社長に就任されました。金融界ではまだ若手の部類に入りますが、心境はいかがですか。
窪田もともと専務時代から戦略、財務、海外と広い範囲を担当してきました。勿論社長という仕事はまったく役割が違いますが、いきなりの就任よりはスムーズに入れていると思います。私は何事も前向きに考えるタイプ。経営企画部などでは歴代の社長の近くで仕事をしていましたが、社長は誰にも相談できず、最後は自分で決断しなければなりません。若い頃から率直に社長に意見もして、ときには怒られてきましたが、私の場合はさまざまな意見をしっかり聞いて決断したいタイプ。今も社長にも正しくモノが言える、話しやすい環境にすることを強く意識しています。

――ご出身はどちらですか。
窪田富山県氷見市です。両親ともに氷見市出身です。氷見は海も山も近く、自然のなかを駆け回っているような子どもでした。運動が得意で、勉強も苦手ではなかったので、周囲から自然と人が集まってくるような感じでした。
小学4年生のとき、父親の転勤で初めて東京に出てきました。まず電車の本数が多いこと、そして人が多いことに衝撃を受けました。地震が頻繁にあることにもびっくりしました。
――その後、どう過ごされたのですか。
窪田少年野球チームに入り、結構強いチームだったので、小学6年生の夏まで野球一色という感じでした。当時、地元の公立中学は校内暴力などで荒れていたので、6年生になってから中学受験を意識するようになりました。毎週日曜日にテストを受けに塾に行く以外は自宅で独学して、記憶力と要領はよかったのか無事合格し、中学校から開成学園に進みました。
開成は質実剛健で自由な学校でしたが、「世のなかにはこんなに頭がいいヤツがいるのか」と中学1年生の段階で悟ることになりました。中学校は1学年300人、高校では100人加わり400人になります。運動会の激しさが有名で、先輩後輩の上下関係が厳しく、高校3年生が中学1年生も指導するのですが、怖かったですね。あとですべて「はったり」だったと分かるのですが、当時はそのようなことは知る由もなく。今でもさまざまな機会で開成の仲間と集まることが多く、いつも運動会の話題になります。同級生の友人でいちばん有名なのは衆議院議員で大阪・関西万博で初代国際博覧会担当大臣を務めた井上 信治君でしょうか。今回も自分の就任お祝い会をやってくれました。ほかにも官公庁や銀行、商社、メーカーなどに同級生が多数いてさまざまな交流をしています。
中学校では当初軟式野球部に入りましたが、途中からTVドラマの影響もあり、ラグビー部に入り直しました。そして結局、高校3年生の春の大会まで続けました。ラグビー部では、「One for All, All for One」の大切さを叩き込まれ、「皆で一つの目標を達成するために一つになる」精神は、社会人になってからもずっと大事にしてきました。

ラグビー部時代。ボールを持っているのが窪田社長。
公認会計士試験に合格
それがきっかけで仕事が広がる
――大学は、東京大学経済学部に進まれます。
窪田大学でもラグビーをしたかったのですが、脱臼癖が治らず断念してラクロス部に入りました。当時のラクロスは日本で始まったばかりで、4年生のときにようやく体育会に昇格しました。練習は週6日、2年生のときには他大学の学生とともに夏休みにアメリカ東海岸へラクロス留学をして、日本でラクロスを広める活動もしていました。ラクロスは朝練が中心。そこで疲れてしまって、授業にはほとんど出ることなく、あとは家庭教師のアルバイトに励んでいました。
ただ、このままではさすがにまずいと思い、手に職をつけるべきだと考え、3年生の途中から1年間休部して公認会計士の受験専門校に通うことにしました。本試験の前の模擬試験の結果は良好で、これをもとに監査法人へ就職活動しました。しかし、自分とはカラーが異なると感じ、同時並行で銀行・生保業界への就職活動も始め、運用部門で会計の知識を生かそうと当時、株式の運用残高が業界最大だった三菱信託銀行に入ることになりました。ちなみに自信満々だった公認会計士2次試験は4年生の段階では落ちてしまい、会社の人事部にも気まずい感じでしたが、翌年入社1年目で合格することができました。落ちたときは相当なショックでしたが、振り返ると「常にうまくいく訳ではない」と、いい経験だったと思っています。
――最初はどの部署に配属されたのですか。
窪田上野支店の法人営業課です。当時の新入社員は通常リテールの営業から始めるのですが、財務が分かるだろうということでいきなり法人営業となりました。新人での法人営業は同期で私だけだったと思います。3年後には大蔵省証券局企業財務課(当時)へ出向となりますが、これも会計士の資格を持っていたからのようです。その後も当時の大蔵省出向時人脈は大変ありがたく、開成人脈と合わせ、今日までさまざまな面でとても役立っています。出向した2年間はとても勉強になりました。よくも悪くも官庁流の仕事の仕方を学んだことで、民間企業のよさも分かりました。会計士はその後3次試験も合格したのですが、結局直接は使わずに今日に至っています。ただ、それがきっかけとなって仕事が広がった意味で、若いときに無理してがんばってよかったです。
――その後、ロンドン支店に赴任されます。
窪田大蔵省の企業財務課で国際会計基準を担当したためか、「国際」つながりで国際業務部に配属されました。周囲は海外帰りや帰国子女ばかりで、私だけ英語の辞書を引くような感じでした。次第に海外に興味を持つようになり、希望が通ってロンドン支店に配属されました。そこで初めて入社時に希望していた運用業務の社債投資に携わることになりました。
実は今の経営会議のメンバーは、当時のロンドン支店・現地法人の出身者が多く、前任の社長もその2代前の社長も当時ロンドンで一緒でした。
土日も仕事で埋まってしまい
家族からは苦情も

――帰国後の2004年には経営企画部統合企画室に配属されます。
窪田これは三菱とUFJの信託合併事務局になるためです。海外からは私のみ、ほかは国内のメンバーでした。辞令があって「すぐ帰ってこい」と言われましたが、こちらは次男がロンドンで生まれたばかり。本来は思い出をつくりながらゆっくり帰国するのですが、慌ただしく2週間で家族ともども帰ってきました。帰国すると統合作業の真っただなかで毎日タクシー帰り。統合作業は全業務にわたるため、各方面と接点を持って交渉しなければなりません。ただ、そこで会社全体のことを把握できましたし、グループ全体のことも理解できました。その後の持株会社や銀行のキーパーソンとも密に連携することができました。
振り返るといちばんの思い出は2005年10月に予定通りきちんと合併できたことかなと思います。妻も仕事をしていましたので子育てが大変で、仕事も家庭も大変忙しい時期でした。土日出社も多く、あるとき仕事が終わり深夜に帰宅すると、玄関ドアにチェーンがかかっていたこともあります(笑)。統合認可を当局から貰えたときは本当にうれしかったですね。そのおかげで、我が家も今日まで続いています(笑)。あのとき、仕事と子育ての両立で苦労をかけた妻には心から感謝していますし、今でもこの話になるとまったく頭が上がりません。
――2000年代以降は経営企画と営業の仕事をおもに経験されています。
窪田経営企画部では全社戦略や中計、財務戦略を練るなど充実していました。次に営業第1部の課長になり、初めて部下を持つ管理職になりました。電力や通信、IT業界を担当し、やりがいも感じていました。2011年の東日本大震災のときはまさに東京電力を担当していたため、ここでファイナンスをがんばらないとインフラが止まってしまう。そんな思いがありました。社会全体の課題に向き合いつつ、仕事を果たしていくことを学ぶことになりました。
――現在、ファイナンス業務は銀行と統合したかたちになっていますね。
窪田経営企画部で次長から副部長になったときに、まさにそのイベントがありました。当初はさまざまな思いがありましたが、今振り返ればあのとき統合してよかったと思っています。ただ、当時の銀行と信託はファイナンスではライバル同士。それを統合することに、社内外で反発がありました。説得を続け、最後には皆が一丸となって2018年4月に統合を果たすことができたときは本当に感慨深かったです。その後、戦略も明確になり、リソースを資産運用・管理、証券代行、不動産などの信託領域にシフトさせ、海外での買収も進めたことで、信託領域をより大きく成長させることができています。
信託のトップランナーとして
デジタル分野でも先陣を切る

――信託は人材が豊富な印象がありますが、人材育成で銀行と信託ではどんな違いがあるのでしょうか。
窪田信託銀行はさまざまな業務を行っています。グローバルでの資産運用・管理、国内では相続や遺言、不動産仲介、企業の株主名簿を管理する証券代行、企業年金など、銀行業務に加えて、幅広いラインナップを有しています。そこには、それぞれの専門家がいます。
その意味で、人材育成はとても重要で、オールラウンダーというよりもさまざまな領域で社会課題解決に貢献できる専門家を育成する必要があります。私のキャリアは多数の領域を経験してきたゼネラリストですが、現在は各領域のスペシャリストが増えています。
ただ、専門性とは、タテの領域を極めるだけでなく、ある程度レイヤーが上がっていくとヨコの領域も広げていく必要があります。ヨコに広げなければ、お客さまのニーズに応えることができませんし、社会課題の解決にもつながりません。今後は、こうしたタテとヨコのバランスをうまく取りながら人材育成を進めていきたいと考えています。
――今、信託ビジネスは社会課題の解決へ向け、大きな期待がかかっていますね。
窪田信託ビジネスは、手間暇がかかるうえ、中長期的な視点が必要な仕事が多いです。だからこそ、私どもはMUFG内で機能別再編という役割分担を行い、信託領域に重点をおいて皆さまの期待に応えていきたいと考えています。たとえば、弊社からスピンアウトさせたデジタルアセットプラットフォーム会社であるProgmat(プログマ)では、ブロックチェーンを使って不動産などの小口化を行い個人投資家のニーズに応える新ビジネスを立ち上げており、こうしたデジタル領域でも先陣を切っています。このように弊社は信託ビジネスのトップランナーとして、あらゆる機会を見逃さず、これからもビジネスを発展させていきたいと考えています。

――最後にメッセージをお願いします。
窪田4月から信託協会会長にも就任しているのですが、信託銀行は日本の金融インフラを担っており、皆さんの知らないところでさまざまなビジネスを行っています。これまでも社会のニーズに合わせ業務を拡大してきました。現在、弊社の粗利益の半分近くは日本以外からとなっています。今後も海外の資産運用、管理領域での拡大を進め、そのノウハウを国内に持ってくることで我が国の「資産運用立国」確立に貢献していきたいです。今後も世のなかの課題解決を少しでも前進させられるよう、信託銀行としての役割をしっかりと担っていきたいと考えています。