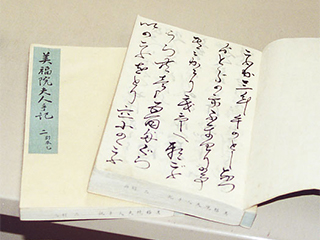三菱人物伝
黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.04 投獄、居村追放
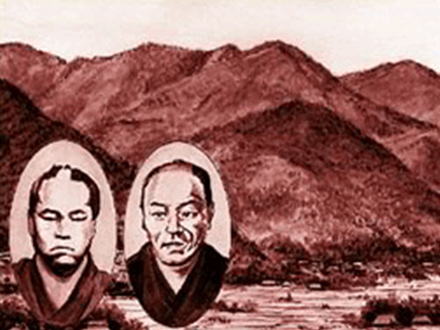
江戸で猛勉強していた彌太郎だったが、我が家の一大事。安政2(1855)年帰国する。田に引く水のこと、年貢のこと、庄屋と百姓たちはことごとくもめていた。それを、彌太郎の父・彌次郎が中に入ってなんとか話をつけた。ところが、手打ちの宴席で言った言わぬで殴り合いになってしまった。泥酔した彌次郎は全身あざだらけ、人事不省になって家に届けられたのだった。
雪の箱根を越え、折からの増水で川止めになって渡れぬ大井川を自ら徒歩で渡りきった。大阪からは船で阿波・土佐国境の甲浦(かんのうら)に渡り、12月29日の夜、わずか16日で土佐の井ノ口村にたどり着いた。
彌太郎は奉行所に訴え出た。しかし、酒癖が悪く、親戚でも鼻つまみ的存在だった彌次郎に味方する者はいない。証人はことごとく庄屋の味方。
「こがなやちもないことがあっても、かまんがか。不正を罷り通すがが奉行所かよ」
「ぬかすな、若僧。そもそも、地下浪人のよ~すでやたらくたら訴えを起こいてお上を騒がすち、まっことけしくりからんぞ」
収まらない彌太郎はその晩、奉行所の壁に墨で「官は賄賂をもってなり、獄は愛憎によって決す」と大書した。彌太郎は治安を乱す者として捕えられ投獄される。
彌次郎は半身不随、彌太郎は獄。次男の彌之助はまだ4歳。岩崎家は悲惨のきわみだった。誰にも相手にされない中で、ただ一人、気を遣ってくれたのが、彌次郎の土地を小作している宅平だった。日ごろの恩を返すのはこういうときだと、美和を助け、彌之助を励まし、農作業や力仕事を手伝った。美和は後年、手記に書いた。「そのとき、幼い彌之助の心持ちは、自然と宅平を親のように頼り、ずいぶん心細く暮らし候」。
入牢体験も糧になった
彌之助も回想している。「母は私を背負い、川のほとりの田地に行き耕しておられた。母は急にめまいがしたのかよろよろと倒れかかり、しばらく地面に座っておられた…」。
ちなみに、この宅平の子孫が、現在高知市に在住し、彌太郎の生家を管理し岩崎家代々の墓を守っている弘田富茂氏である。岩崎家の名代として安芸市や菩提寺である閑慶(かんけい)院との関係にも心をくだいている。
さて、獄中の彌太郎は居ても立ってもいられない。しかし、未決のままお上からは何の音沙汰もなく時間だけが過ぎて行く。彌太郎は母に手紙を書く。「…私の出牢いたし候をお待ちつかわされたく、…決してお元気をお落としつかわされな…」。結局、彌太郎は7か月獄につながれたあげく、家名削除・居村追放となった。
獄中、反骨精神は彌太郎の骨の髄まで染み込んだ。ひまつぶしに同房の商人から算術を学び、商売の機微を教えられた。彌太郎の将来に大きな影響を与える入牢体験になったのだった。
井ノ口村を出た彌太郎は高知城下にほど近い村に移り寺子屋まがいのことをしながら生計を立てた。年末、彌太郎はようやく追放赦免・家名回復となったが、村へは帰らず、そのまま吉田東洋の少林塾に入門した。
東洋は卓抜した識見の士。水戸藩の藤田東湖とともに全国にその名を馳せた。当時は長濱(ながはま)村に蟄居(ちっきょ)中で、少林塾を開いて若者たちに影響を与えていた。彌太郎はこの少林塾で後藤象二郎と親交を持つようになるとともに、その明晰さゆえに東洋に目をかけられる。
江戸では彦根藩主井伊直弼が大老に就任、勅許を待たずに日米修好通商条約に調印した。(つづく)
文・三菱史料館 成田 誠一
- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2002年8月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。