
三菱人物伝
黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.24 彌太郎の遺産(最終回)
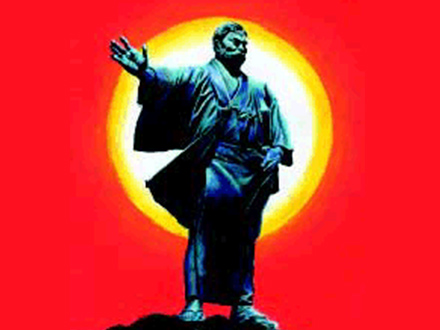
幕末の土佐の田舎の腕白坊主。よく村の裏山に登った。遥かに広がる黒潮の海を見ながら、まだ見たことのない広い世界に夢を膨らませた。水平線には大きな積乱雲が湧きあがっていた。
岩崎彌太郎。明治3(1870)年、35歳で大阪に九十九商会を創設し、わずか5年で日本の海運業界の覇者となった。そして10年、あたかも太陽に挑むように前向きに生きた彌太郎だった。
立ち止まることを知らなかった。出る杭は打たれるの喩えの通り、毀誉褒貶(きよほうへん)種々あったが一歩も譲らなかった。自らの信念を貫いた。
茅町本邸の死の床で、おそらく彌太郎は、自分の人生で出会った数多くの人たちを思い出したことだろう。
吉田東洋、武市半平太(たけちはんぺいた)、後藤象二郎、ジョン万次郎、坂本竜馬、トマス・グラバー、ウォルシュ兄弟、板垣退助、谷干城、大久保利通、大隈重信、福沢諭吉、伊藤博文、井上馨、西郷従道、渋沢栄一、松方正義…。波瀾に満ちた、密度の濃い人生だった。
明治18(1885)年2月7日、50歳で息をひきとる直前まで、彌太郎の意識はしっかりしていた。激痛にうめきながら言った。
「…志したことの十のうち一か二しか出来ないうちに、こんなことになってしまった。いかんともしがたい。…彌之助、川田(小一郎)よ、わしの志を継ぎ、事業を、しっかりたのむぞ。いいな…。ううう…、ハラの中が裂けるように痛い。もう、何もいわん」
彌太郎の遺志に従って三菱は彌之助が引き継ぎ、川田が支えた。さらに久彌、小彌太が継承し、日本の近代化と軌を一にして歩んだ。そして、世紀を二度跨(また)いで今日の三菱グループとなった。
武士の心
彌太郎は武士の心にこだわった。三菱の飛躍的発展のきっかけとなった明治10年の西南戦争は、特権的役割を終えた武士たちの誇りと意地を賭けた戦いだった。負け組の無念の思いは勝ち組に心の痛みとして引き継がれ、近代国家日本のいしずえとなった。勝ち組の軍事輸送を担った彌太郎だったが、生涯を貫いたものは、「義」と「国のため」を旨とした「明治の武士道」だったと言って良い。
その精神は、『所期奉公』の精神として代々引き継がれていった。期するところは国のため、社会のため。これこそ三菱の心である。
時は下って太平洋戦争勃発の翌々日、三菱の四代目総帥岩崎小彌太は幹部社員を集め、「(これまで自分はリベラルな発言もしてきたが)国の目指すところが決まった以上、国民の義務として、三菱の総力をあげて生産に励もう」との基本姿勢を明示した。同時に、「法が許す限り(これまで事業を提携してきた米英の友人たちの)身辺と権益を守ることは日本人の情義であり責務である」と、特高の目を恐れることなく訓示した。座標軸のぶれない、彌太郎以来の三菱の総帥ならではの見識だった。
文明は限りなく発達し、彌太郎少年が黒潮の海の果てに夢を膨らませた世界は、いつでも手が届くようになり、人類は宇宙にまで活動の場を広げている。であれば、彌太郎がこだわった『所期奉公』の精神は、今や、「世界のため、宇宙のため」と解釈すべきだろう。
岩崎彌太郎、駒込の染井の墓地に眠る。が、その心は染井にとどまっていない。彌太郎の遺産として三菱の各企業に受け継がれ、正々堂々の活動の中に永遠に生きている。
文・三菱史料館 成田 誠一
- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2004年4月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。
