
トンネルを抜けて少し坂を下ると、突如として巨大な塔が現れる。高さ64mのその鉄の塔は、そこに至るのどかな林野風景とは明らかに異質である。だがしかし、その塔とロータリーキルンこそセメント工場の中核設備であり、その地に恵みをもたらした殖産興業の象徴である。
UBE三菱セメント岩手工場は、JR一ノ関駅から車で東北東へ20分程度。タクシーに乗り込み、行先を告げると、運転手は無線で「マテリアル」と本部に報告した。2022年に発足する前の三菱マテリアル時代のなごりなのだろう。
同地はもともと1936年に設立された国策会社、東北興業株式会社が発祥である。1957年に東北開発株式会社に改組され、セメント会社となり、1986年に同社は民営化された。1991年に三菱マテリアルと合併。その後、2022年に三菱マテリアルのセメント事業と宇部興産(現UBE)の建設資材事業が統合され発足したUBE三菱セメントに移管された。現在の岩手工場で働く者は140名程。同社社員24名とグループ企業のマテリアル東北77名ほか、協力会社で運営されている。
近くには日本百景・国の名勝である猊鼻渓(げいびけい)があり、砂鉄の川が石灰石を浸食してできた渓谷が2kmあまり続く。その近くに岩手工場があるということは、セメントの原料である石灰石が周辺に豊富であることを示している。
実際、岩手工場は原料立地型内陸工場という特徴がある。工場に隣接する長坂鉱山からセメントの主原料である石灰石を採掘できるため、輸送コストがかからない。セメント工場としての規模は日本で小さい部類といわれるが、良質な石灰石をもとに、多品種のセメントや石灰石製品を生産している。高度なリサイクル技術を駆使し、多様な廃棄物をセメント原料および熱エネルギーに代替し有効活用しており、カーボンニュートラルの時代を先取りする取り組みも早くから行われている。
長坂鉱山で採掘した石灰石は工場に輸送され、原料工程・焼成工程、仕上工程を経てセメント製品が製造される。焼成工程のプレヒータとキルン(焼成窯)で原料粉末を加熱、焼成してセメントのもととなるクリンカと呼ばれるものをつくる。加熱することで水と練ると固まる特性を有するこのクリンカを石膏と混合し細かく粉砕することでセメントになる。稼働中は、巨大なドラム缶のようなキルンをゆっくり回転させながら最高1,450℃の高温で焼成するため、キルンの周囲は常夏のようである。その圧倒的な空気感、スケール感こそが、ここがセメント工場であることを実感させてくれる。また、原料・熱エネルギーの代替として使われる廃タイヤや廃プラスチックなども工場内に保管され、多様な廃棄物が有効に活用されていることが分かる。
岩手工場は東北近隣のセメントの一大供給地となっている。一般の土木・建設工事向けをはじめ、ダムや河川、港湾などの土木工事向け、道路や橋梁工事に向けたものなど、まさに日本のインフラを担っているセメント・石灰石製品を生産している。そんなUBE三菱セメント岩手工場で働く皆さんをこれから紹介していこう。
採掘では長期運用を見据えた指揮管理に加え、
操業コスト低減の取り組みも必要

採鉱課採掘係で働く髙山 啓さんは入社7年目。今年3月から岩手工場に勤務している。
「石灰石鉱山の安定操業実現のため、火薬類を用いた原石の採掘、大型重機を使った原石の積込運搬、プラントでの製品生産から出荷までといった一連の工程管理を担当しています。操業管理を行ううえでは何ひとつ欠くことはできないので、総合的な知見が必要になってきます。多角的に工程を見ながら問題を解決していく”何でも屋さん”といえるでしょう」
石灰石鉱山で仕事をする面白みとは何だろうか。
「自然が相手なので、思うようにならないところでしょうか。広大な鉱山というフィールドで原石の性状や品位などを見極めながら、いかにスマートに採掘を進めていくか。もちろんコスト面からもバランスよく動かすことが重要になりますので、広い視野と知識と経験がものをいう世界だからこそ面白い」
大学では地質学を学び、今の仕事の現場では、予見が難しいトラブルを、いかに予防できるかを重視する。だからこそ、安定的に生産できていることがうまくやれている証左であるし、何よりやり甲斐でもある。それこそが社会から求められていることだと思うとさらに身が引き締まる。
「鉱山といっても有限ですから、採掘では長期運用を見据えた指揮管理に加え、操業コスト低減の取り組みも必要になってきます。各鉱山が抱える懸案事項はそれぞれ異なります。長坂鉱山では品質のいい石灰石が採掘できる分、いかに生産効率を上げるかが課題となっています」
休日は釣りやキャンプを楽しんで過ごすという髙山さんは、今後どのようなキャリアを築きたいと思っているのだろうか。
「当社には全国にさまざまな石灰石鉱山があります。いろんな拠点があるなかで、どのように生産し出荷していくのか。長期的な視点が欠かせません。そうしたロードマップや方針を立て、フォローしていくような仕事がキャリアの到達点だと考えています。何事も責任感をもって仕事をやり抜く人になりたいですね」

岩手工場の総務課経理係で働く伊藤 駿也さんは入社6年目。現在は、経理として製造原価をとりまとめながら、工場の月次決算資料の作成や予算作成を行っている。
「各課から上がってきた数字をデータに落とし込み、そこから原価計算を行い、資料を作成します。計算された数値を基に分析を行い幹部へ報告、本社へ提出しています。まさに岩手工場の実態を可視化し、経営判断を支える“財務の眼”としての機能であり、事務職として工場の操業に携われていることに面白みを感じています」
続けて、
「すべての工程とかかわることになるので、各部署とどうコミュニケーションをとっていくのかが大事になります。まだ勉強不足のところもあり、セメント製造にかかわる専門的な用語が出てくると話が中断しますが、そこでしっかりと相手に向き合い理解することで更に仕事の質が上がっていくことを実感しています」
伊藤さんは昨年12月に岩手工場に着任したばかりだが、職場の雰囲気は和気あいあいとしていながら、締めるところはしっかり仕事をする、メリハリのあるところが気に入っている。半年以上が過ぎ職場にも慣れて、より責任感を持って自分らしく仕事に携われるようになったそう。プライベートでの趣味はバドミントン。地域の人達と楽しみ、ときには大会にも出場するという。
「自分としては、もっと現場と距離の近い経理パーソンでありたいと思っています。本社と現場をつなぐ存在でありたい。コミュニケーションを大事にしながら、現場から信頼され、『このことなら伊藤に聞け』と言われるような頼られる人になりたいです」
勤続18年で改めて感じることは、
やはり当社は日本のインフラを支えているということ
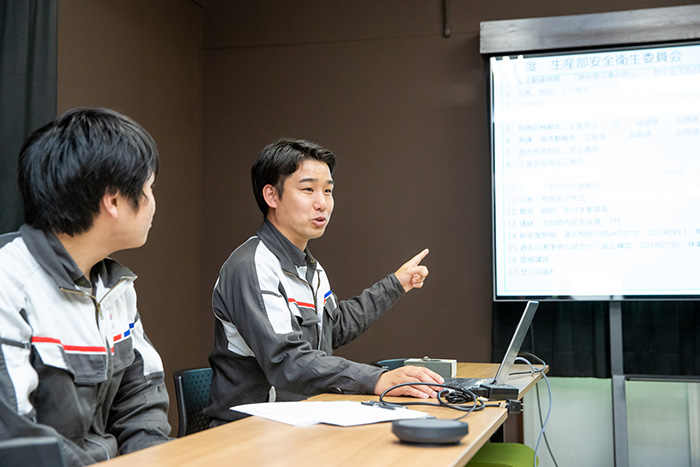
総務課原燃料リサイクル係の古賀 弘朗さんは入社18年目。地元の九州工場に長年勤務しており、岩手工場に来てから6年ほどになる。赴任して最初に感じたのは「寒い」こと。今でもとんこつラーメンは時折恋しくなる。
そんな古賀さんは現在、グループ企業のマテリアル東北とともに業務を進め、セメント製造に必要な原料・熱エネルギーおよび廃棄物の調達や受入れの管理、また取引先の情報収集などの仕事に従事している。
「我々の仕事は、工場操業の根幹を支える“血管”のような存在です。原料・熱エネルギーおよびその代替物である産廃を適切なタイミングで適切な品質、価格で調達することで、工場の『生命活動』を維持しています。さらに、外部との契約や調達条件の管理を通じて品質・コスト・納期のバランスをとる“門番”としての役割も果たしています。廃棄物はセメントの原料代替物になりうるかの分析を行う必要があり、生産課でのハンドリングなども考慮し厳格に選別する必要がある一方、より多く受け入れる必要がありますので、幅広い企業や団体に出向き情報を収集しています」
廃棄物を集める営業の仕事をはじめ、これまで古賀さんはさまざまな業務を担ってきた。そうした経験を生かして、もっと仕事の幅を広げていきたいと語る。
「勤続18年で改めて感じることは、セメント産業並びに当社が日本のインフラを支えているということです。廃棄物のセメントへの再資源化を通じて循環型社会の構築に貢献している。その意義は大きいと感じていますし、それにかかわって仕事ができることに誇りを持っています」
古賀さんは今後も営業の仕事で培ったコミュニケーション力をもとに、自身を軸として会社や社員、お客さまといったステークホルダーが満足いく仕事をしていきたいという。

生産課電気係に勤務する千葉 禎さんは入社40年目、岩手工場一筋の大ベテランだ。現在は工場、鉱山電気設備の保守保全や新規工事、補修工事の計画、進捗管理および検収などに携わっている。
「工場、鉱山電気設備の故障を予防し安定操業に貢献する役割を担っています。人手不足のなか、保守保全が疎かにならないように気を付けています。電気は365日受電しているため、設備故障があれば迅速な対応が必要になります。故障したら長期的に使えなくなるものもあり、とくに重要な設備については定期的な点検や診断を欠かさないようにしています」
保守保全では更新のタイミングに苦慮しています。使えるものは少しでも長く使いたいがコストダウンもしていかなければいけない。設備と対話してその具合を見極めながら、更新のタイミングをはかる、そんな勘所が大事になるという。
「これまでの経験のなかで、最も大変だったのは洪水と地震のときです。工場に隣接する砂鉄川と山谷川が増水し工場に流れ込み、敷地全体が濁流にのみこまれました。地上の水は1日で引いたものの、地下の水は数日かけてポンプで汲み上げなければなりませんでした。設備を復旧できるのか、工場閉鎖になるのではないかと危惧しましたが、工場・鉱山・協力会社が一体となり懸命に復旧活動を続け、何とか2カ月後に操業再開となりました。そのときは涙が出ましたね。一方、東日本大震災では工場施設、建造物に被害がありましたが、幸いにも人的被害はありませんでした。1カ月もかからず設備復旧できたことも幸いでしたね」
千葉さんは来年60才。いずれは電気主任技術者の資格を生かした仕事をしてみたいという。そんな千葉さんは後輩達に次のようなメッセージを送る。
「皆さんとともに仕事をする時間はもうそれほどありません。会社人生は山あり谷ありですが、潮目の悪いときでも決して挫けずに、前を向いて前進してほしい。そう願っています」、眼鏡の奥に潜むやさしい視線が印象的だった。

髙山 啓
KEI TAKAYAMA
採鉱課採掘係

伊藤 駿也
SHUNYA ITO
総務課経理係

古賀 弘朗
HIROAKI KOGA
総務課原燃料リサイクル係

千葉 禎
TADASHI CHIBA
生産課電気係



