
三菱人物伝
黒潮の海、積乱雲わく ―岩崎彌太郎物語vol.07 坂本竜馬と彌太郎
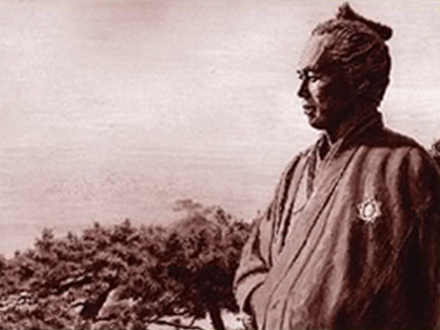
坂本竜馬は、岩崎彌太郎が井ノ口村に生まれた翌年の天保6年11月15日(1836年1月3日)、高知城下の、郷士で御用商人でもある裕福な家に生まれている。文久2年、26歳で脱藩した竜馬は勝海舟(かつかいしゅう)に出会い、「日本の洗濯(改革)」を決意する。西郷隆盛の支持を得て長崎に亀山社中(かめやましゃちゅう)を結成、薩摩を始め諸藩の貨物輸送にあたるかたわら薩長同盟を演出、幕末の混乱の中で縦横無尽の活躍をした。
その竜馬が土佐藩参政である後藤象二郎と意気投合、竜馬と中岡慎太郎は脱藩赦免状を得、亀山社中の船隊は海援隊となる。一方、慶応3(1867)年、長崎商会に赴任した彌太郎は象二郎を輔(たす)け、土佐藩のために金策に走り、蒸気船や武器弾薬を買いつけ、さらには海援隊の活動をも支えた。
経済官僚として奔走する彌太郎と自由な立場で政治改革を志向する竜馬。活動の内容は大いに違ったが、常に広い世界を意識していた点ではおそろしく共通していた。
司馬遼太郎の『竜馬がゆく』で竜馬は国民的英雄になったが、彌太郎は引き立て役を演じさせられ大分損をしている。しかし、彌太郎の日記を見ると、たとえば慶応3年6月3日、「天気快晴…午後坂本竜馬来たりて酒を置く。従容(しょうよう)として心事を談じ、かねて余、素心(そしん)在るところを談じ候ところ、坂本掌をたたきて善しと称える」とある。肝胆相照らすものがあったのであろう。
風雲急を告げていた。雄藩(ゆうはん)は討幕に向けて準備を進めている。京都では山内容堂(ようどう)、島津久光、松平春嶽、伊達宗城(だてむねなり)の四侯が会談し策を練るが纏(まと)まらない。容堂は象二郎と竜馬の意見を求めた。二人は急遽京都に向かう。
上洛する竜馬と象二郎を見送った彌太郎は日記にこう記した。「(慶応3年6月)9日、雨。…午後(象二郎と竜馬は)睡蓮(スイレン)船(のちの藩船夕顔)に乗る。商会の高橋が随行。…2時、これ出帆なり。余および一同これを送る。余、不覚にも数行の涙を流す…」
長崎で活躍する彌太郎
さあ、大政奉還のシナリオが動き出す。「象二郎よ、竜馬よ、頼むぞ」との思いだったのだ。
この船の中で竜馬は、いわゆる『船中八策』をまとめた。「天下の政権を朝廷に奉還せしめ、政令よろしく朝廷から出ずべきこと。上下議政局を設け、議員を置き、万機を参賛(さんさん)せしめ、万機公論に決すべきこと…」で始まる、新しい国のグランド・デザインである。これは象二郎から容堂に建言され、容堂から徳川慶喜への建白書となって、歴史を大きく動かすことになる。
長崎商会の後事は彌太郎に託された。留守居役への郷士の起用。象二郎の信頼の厚さを示していた。
彌太郎は、竜馬が長崎を離れてからもいろは丸事件※1で紀州藩と粘り強く交渉を続けて多大な賠償を取りつけるなど、引き続き海援隊の面倒をみた。また、英国人殺傷事件で土佐藩にあらぬ嫌疑がかかると英国公使を相手に一歩も妥協しなかった。
一方、竜馬は京都に出て半年、薩長土を主役とする維新の舞台回しの中で無念にも暗殺されてしまう。新しい日本のあり方を建策し、その実現に邁進しながら、自らその結果を見届けることは叶わなかった。
七つの海に乗り出すことを夢見ていた竜馬。歴史に「イフ」はないが、もし竜馬が明治の世にも生きていたら、海運を取り仕切り、貿易を手掛け、産業を興して、彌太郎三菱の強力なライバルになっただろう。(つづく)
-
※1
海援隊が大洲(おおず)藩から借りていたいろは丸が紀州藩の船と衝突し沈没した事件。
文・三菱史料館 成田 誠一
- 三菱広報委員会発行「マンスリーみつびし」2002年11月号掲載。本文中の名称等は掲載当時のもの。