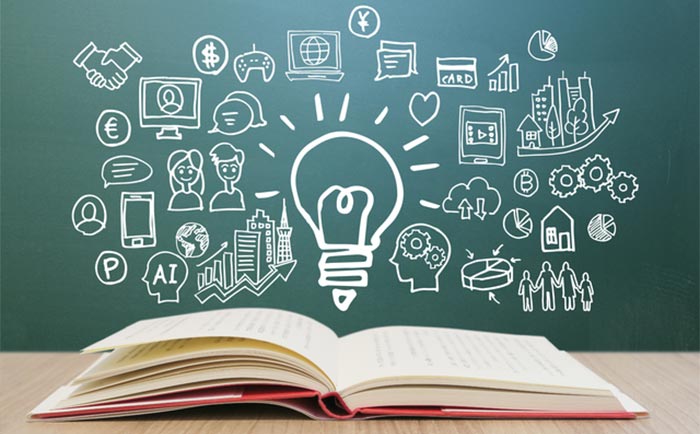
ビジネスの最前線で舵をとる三菱グループ各社のトップ達は、どのような本に触れ、そこから何を学んでいるのか――。読書の秋に向け、19人の社長が「生き方や仕事を支えてきた一冊」「今、読むべきと感じている一冊」を紹介する。ジャンルはビジネス書にとどまらず小説やエッセイなどさまざま。それぞれの選書とコメントからは、未来を見据えるリーダーの思考の原点が垣間見える。ページを繰れば視野が開け、これからの時代を生き抜くヒントが見つかるに違いない。
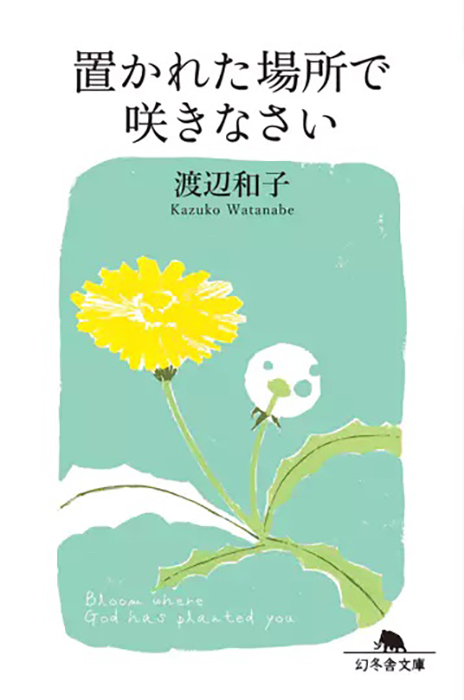
■『置かれた場所で咲きなさい』渡辺 和子(幻冬舎文庫)

アストモスエネルギー 代表取締役社長
山中 光 MITSURU YAMANAKA
著者の渡辺和子さんはカトリックのシスター。9歳のとき、2.26事件で惨殺される父上の渡辺錠太郎大将を目の前で見ていたという悲惨な体験をお持ちです。書籍名も印象に残る言葉ですが、私は「時間の使い方はいのちの使い方」という書中の至言を社員に伝えています。ご職業柄、やや宗教色は感じますが、3~5ページの短文とともに味わい深い一言ずつで構成されており、大変読みやすい書籍です。「今日という日は自分が一番若い日」とあとがきに残されています。
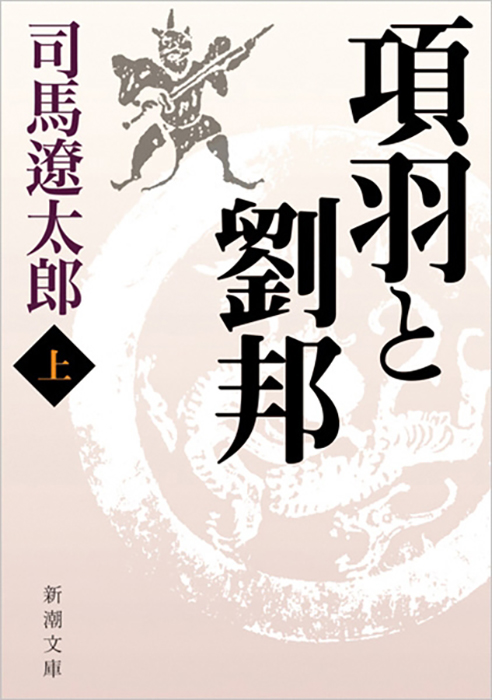
■『項羽と劉邦』司馬 遼太郎(新潮文庫)

AGC代表取締役・社長執行役員CEO
平井 良典 YOSHINORI HIRAI
学生の頃に初めて読んで以来、何度も読み返してきた特別な一冊です。項羽と劉邦は、それぞれまったく異なるリーダー像を持つ人物として描かれ、私は劉邦のリーダーシップに魅力を感じました。多様な人財を生かしながら成果を上げる姿は、現代の経営や組織運営にも通じるものがあります。また、二人の英雄を支える個性豊かな人物達も多数登場します。「自分は誰に共感するか?」と考えながら読むのもひとつの楽しみ方です。これまで何度か読み返すなかで毎回新しい気づきを得ています。
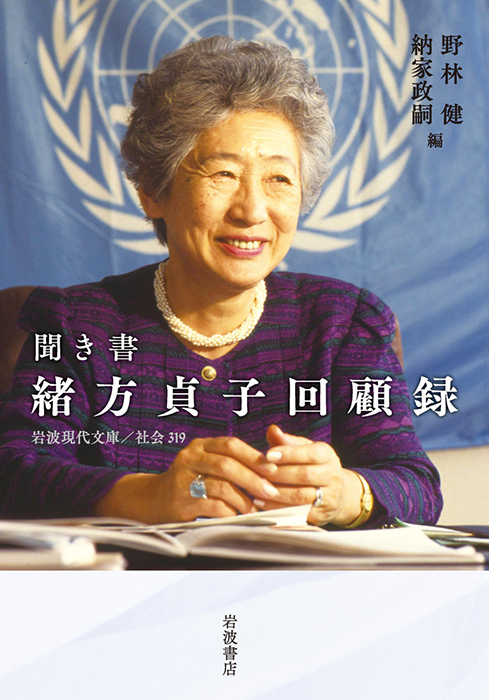
■『聞き書 緒方貞子回顧録』緒方 貞子、野林 健、納家 政嗣(岩波現代文庫)

キリンホールディングス 代表取締役社長COO
南方 健志 TAKESHI MINAKATA
緒方さんの一貫した仕事に対する姿勢、行動は、規範に囚われない生き様を示唆しています。時代の波に押される形で国連の最前線に立たれ、未経験の仕事も前向きに受け止めて現場に飛び出し、人命尊重の姿勢を貫いて現場主義と即決主義を実践されました。その人間性に加え、傾聴、対話の努力によって世界の人々の信頼を獲得したことは、リーダーは組織の多様性の強みを引き出すことが重要であると教えてくれます。
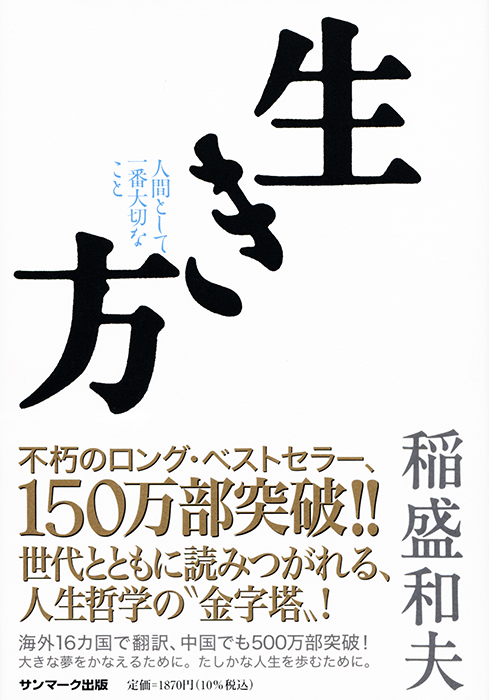
■『生き方 人間として一番大切なこと』稲盛 和夫(サンマーク出版)

大日本塗料 代表取締役社長
里 隆幸 TAKAYUKI SATO
人生の正しい生き方や人間として一番大切なこと、生きる意味と人生のあり方を根本から説いた一冊。悩んだとき、不安なときに何度も読み返し、エネルギーをいただいています。稲盛和夫氏の書籍は多数出版されていますが、私にとって最も感銘を受けた一冊です。同氏の実体験に根ざした言葉はどれも深く心に残り、読むたびに大切なことに気づかせてくれます。
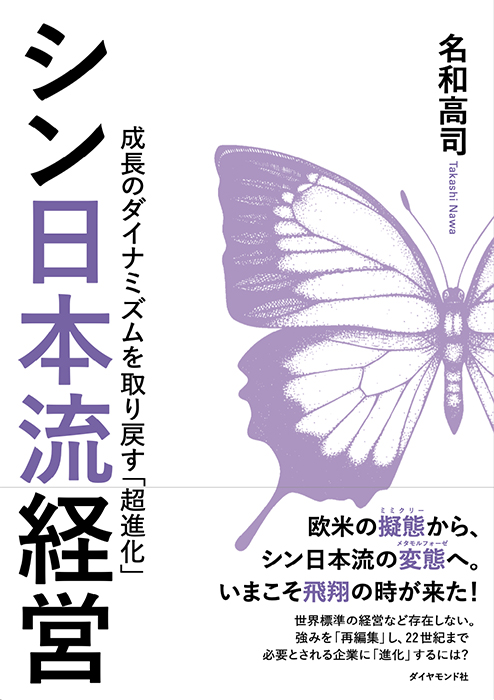
■『シン日本流経営 成長のダイナミズムを取り戻す「超進化」』名和 高司(ダイヤモンド社)

東京海上日動火災保険 取締役社長
城田 宏明 HIROAKI SHIROTA
芸道や武道の修行プロセスを表す「守破離(しゅはり)」が、日本流経営の進化のリズムとして紹介されています。私自身も小学2年生から剣道の稽古に励んでおり、この「守破離」の考え方が好きで、社内でも頻繁にこの言葉を使っています。「離」はイノベーションとも言えますが、独自の強みや伝統を忘れずに、「守破離」のプロセスを繰り返すことで、初めて「離」に到達できるという考え方にも強く共感しています。
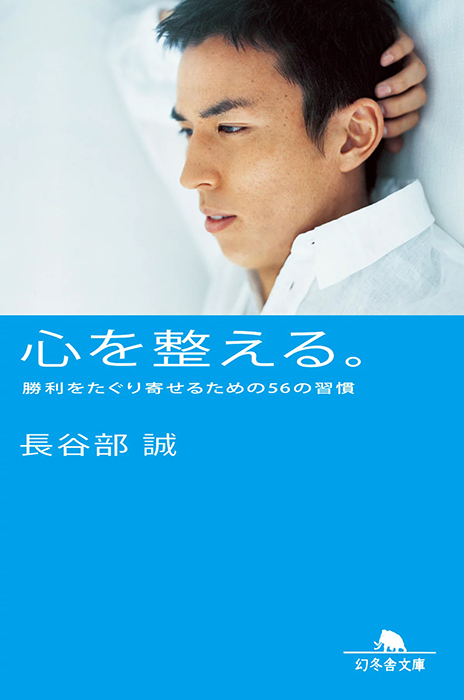
■『心を整える。 勝利をたぐり寄せるための56の習慣』長谷部 誠(幻冬舎文庫)

三菱HCキャピタル 代表取締役 社長執行役員
久井 大樹 TAIJU HISAI
あまり本を読まない私がこれまでに読んだなかで記憶に残っている本。長くサッカー日本代表キャプテンを務めた長谷部誠さんが、2010年ワールドカップで初めて代表キャプテンを務めた直後、27歳のときに書いたもの。私自身、マネジメント・ポジションに就いた初期の頃に手にした本でしたが、まったく異なるフィールドとはいえ、チームを引っ張る立場の人間として、心を調整・調律する、メンテナンスするといった意味での「心を整える」ことの大切さを学びました。長谷部さんの「僕自身、自分が未熟で弱い人間だと認識しているから『心を整える』ことを重視している」というコメントが印象的。
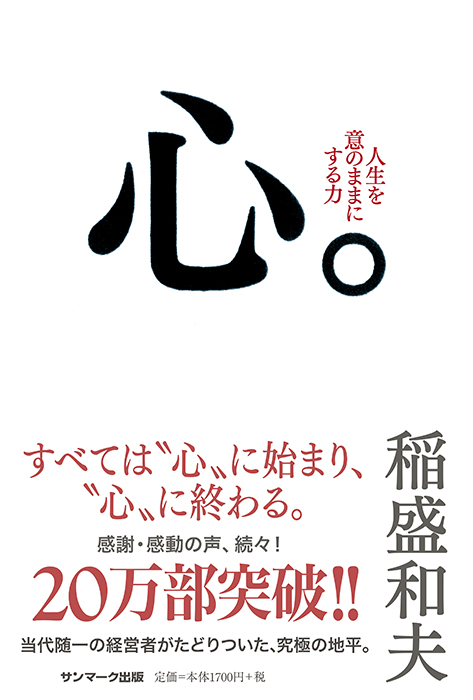
■『心。』稲盛 和夫(サンマーク出版)

三菱化工機 代表取締役 社長執行役員
田中 利一 TOSHIKAZU TANAKA
人間の過ち、おごりや高ぶり、事の不成功、ストレスとなる人間関係など、みんな自己愛、私心、利己が生み出す弊害です。一方、他者を思いやるやさしい心、ときには自らを犠牲にしても他のために尽くそうと願う心、「利他」の心を動機とする判断基準、言動は、結果として成功する確率が格段に高い。そして感謝の心を忘れない。もし、結果として成果が出なくても後悔することはありません。仕事も私生活もすべての行為において通じることです。閉塞感を感じたらぜひ読んでみてください。
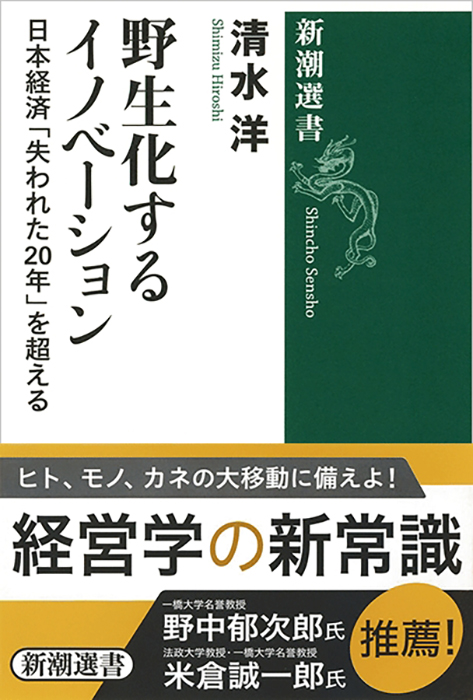
■『野生化するイノベーション―日本経済「失われた20年」を超える―』清水 洋(新潮選書)

三菱ガス化学 代表取締役社長
伊佐早 禎則 YOSHINORI ISAHAYA
「野生化」という視点から、イノベーションの本質や日本企業の課題を分析し、成長戦略の見直しを提言しています。日本の経済停滞の原因を「イノベーション不足」と位置づけ、企業の硬直化や人材の流動性の低さが成長を阻害していると指摘していて、弊社の新規事業の創出の難しさを認識しました。また、イノベーションを促進するためには企業や政府がどのように対応すべきかを提案しています。イノベーションの「野生化」が進むことで、企業が短期的な利益を優先し、長期的な成長のための基礎研究が軽視されるリスクについても警鐘を鳴らしており、研究開発を成長の軸に据えるメーカーにとっては刺さります。
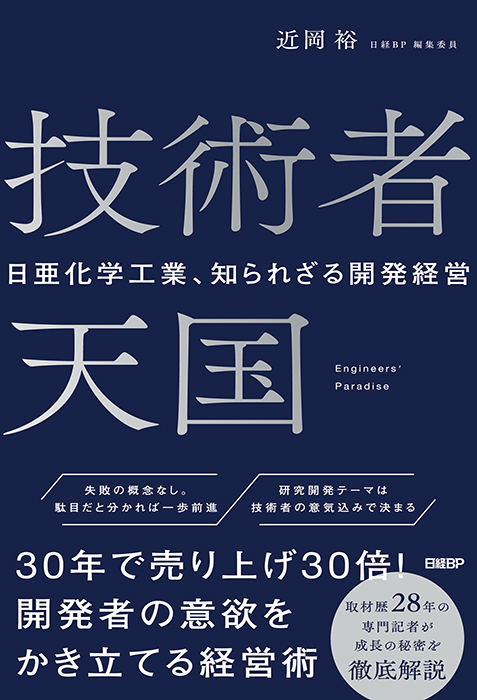
■『技術者天国 日亜化学工業、知られざる開発経営』近岡 裕(日経BP)

三菱ケミカルグループ 代表執行役社長
筑本 学 MANABU CHIKUMOTO
日亜化学工業には「失敗」という概念がなく、失敗を前向きな学びと捉える企業文化を持っています。研究者の情熱を何よりも重視し、意気込みによって投資を決定する。これにより失敗を恐れずに挑戦を続ける文化が根付いているのです。同社の企業文化からは「人生の目的と会社の目的が一致したとき、人は最大限の力を発揮できる」という示唆が得られます。研究者だけでなくすべてのビジネスパーソンに読んでほしい一冊。
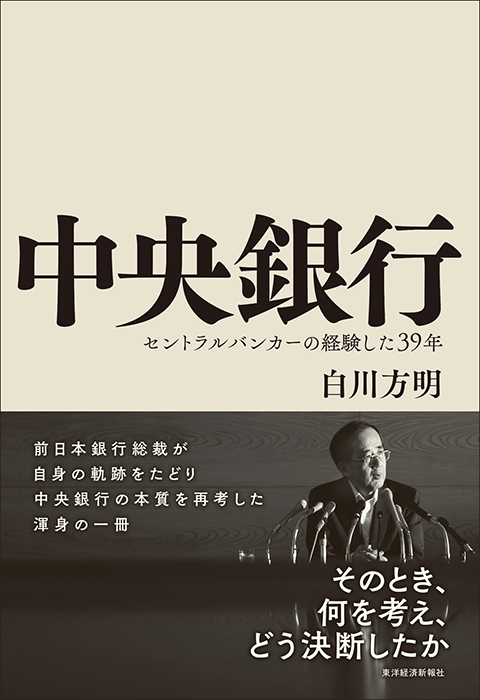
■『中央銀行 セントラルバンカーの経験した39年』白川 方明(東洋経済新報社)

三菱地所 執行役社長
中島 篤 ATSUSHI NAKAJIMA
白川元日銀総裁が書かれた本書が素晴らしいものでした。私も経験してきた経済の大きな浮き沈みのなかでセントラルバンカーが何をどのように考え、行動してきたのかを理解できることもさることながら、そもそも中央銀行とは何か、どうあるべきなのか、という事を改めて考えることができます。わが国では日本銀行、アメリカでは FRB などが難しい局面にある現状において大変示唆に富む書籍です。
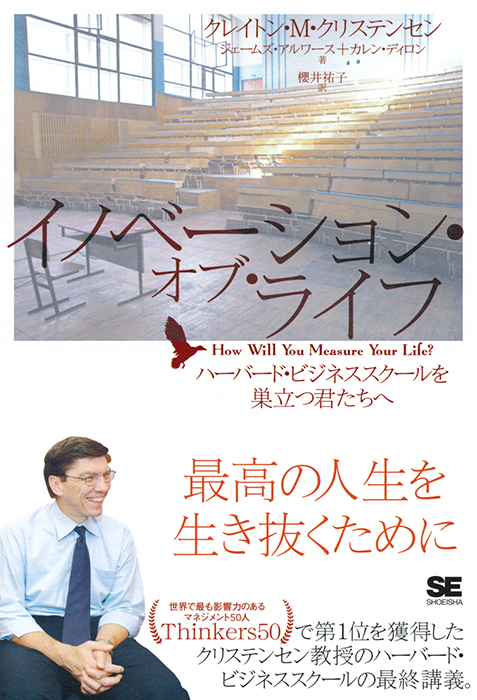
■『イノベーション・オブ・ライフ ハーバード・ビジネススクールを巣立つ君たちへ』クレイトン・M・クリステンセン、ジェームズ・アルワース、カレン・ディロン、櫻井 祐子訳(翔泳社)

三菱食品 代表取締役社長
京谷 裕 YUTAKA KYOYA
「破壊的イノベーション」で有名なHBSのクリステンセン教授(2020年逝去)の「最後の授業」といわれる少し古い本ですが、これまでの「自由主義・民主主義・資本主義」的価値観の再定義が必要なほど混沌としている今だからこそ、改めて読み返し、皆さんの人生において最も重要なこと(人生を測るものさし)を考える絶好の機会を提供してくれると思います。
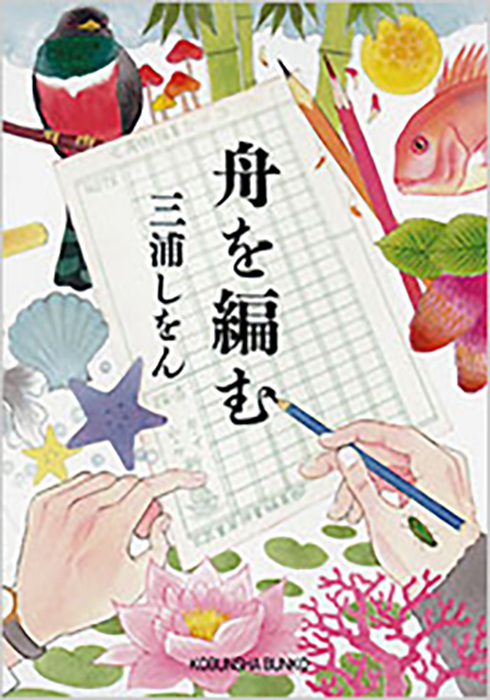
■『舟を編む』三浦 しをん(光文社文庫)

三菱製紙 代表取締役社長
木坂 隆一 RYUICHI KISAKA
辞書編纂を通じて、人間関係や人生の課題に向き合っていく姿を描いた作品です。書籍を世に送り出すまでにはいくつもの工程を経ますが、それぞれの工程で専門知識を共有し議論を重ねる姿から、言葉の持つ力や、人と人とのつながりの重要性を感じることができます。この本は、映画、アニメ、ドラマ化がされているので、各媒体での描き方の違いも面白いです。単行本の書籍用紙には当社製品が採用されております。
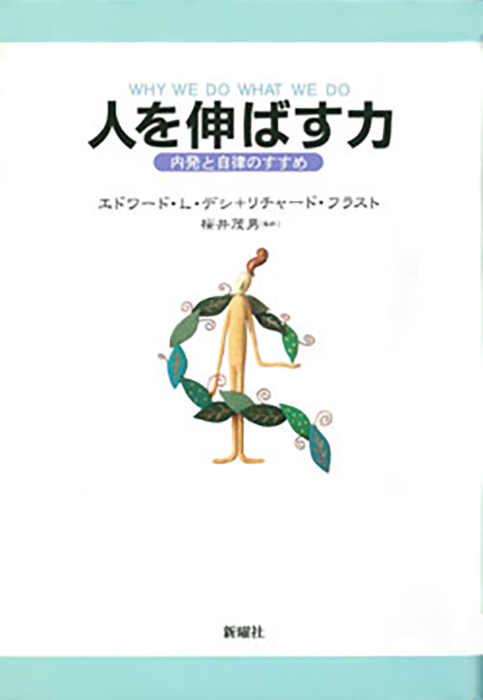
■『人を伸ばす力 内発と自律のすすめ』エドワード・L・デシ、リチャード・フラスト、桜井 茂男監訳(新曜社)

三菱倉庫 代表取締役社長
斉藤 秀親 HIDECHIKA SAITO
エドワード・L・デシは、内発的動機を研究した米国の心理学者です。モチベーションには、報酬など外発的動機と自らの心から湧き上がる内発的動機がありますが、自律性と自己効力感を高めることで、「自分の行為の主人公が自分自身であることを実感できる」とともに、創造性や責任感、持続性も高まるとしました。本人の幸福感が上がるとともに、組織の成長にもつながるわけです。働く人すべてにおすすめしたい本です。
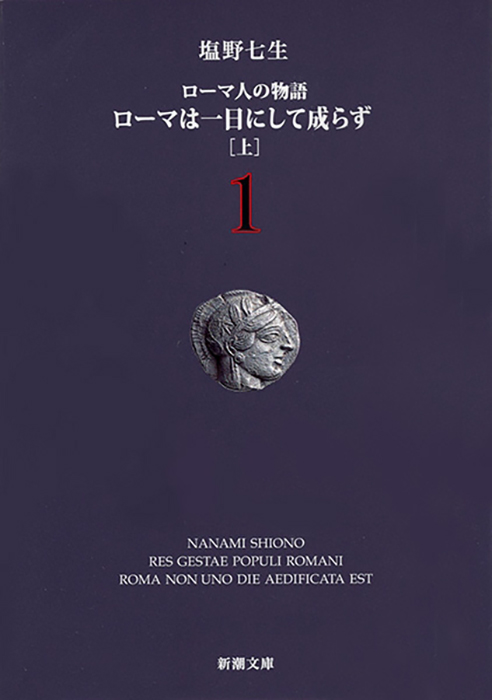
■『ローマ人の物語』塩野 七生(新潮文庫)

三菱総合研究所 代表取締役社長
籔田 健二 KENJI YABUTA
子どもの頃から歴史小説が大好きで、山岡 荘八、吉川 英治、司馬 遼太郎、池波 正太郎などを読み漁ってきました。『ローマ人の物語』は、銀行役員時代に大企業担当で海外出張を繰り返していた頃の「機内の友」でした。スキピオとハンニバルの死闘、カエサル/アウグストゥスの栄光、五賢帝の苦悩、衰退期の皇帝の苦闘などが、出張の記憶とともに懐かしく思い出されます。
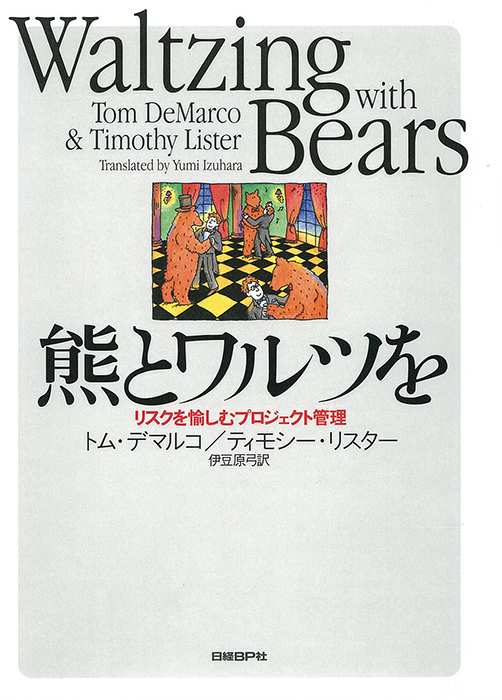
■『熊とワルツを リスクを愉しむプロジェクト管理』トム・デマルコ、ティモシー・リスター、伊豆原 弓訳(日経BP)

三菱プレシジョン 代表取締役 取締役社長
若菜 健司 KENJI WAKANA
「プロジェクトでは勝つために特別なことをするより、負けの程度を抑える方が大事」。プロマネ時代に出合った一冊。リスク(熊)とのつき合い方を論理的に、ユーモラスに解説し、プロジェクトにおける不確定性を数量化し可視化する手法を紹介しています。はじめは現実のプロジェクトへの適用に半信半疑でしたが、米国宇宙機器メーカーが実践しているのを見て考えを改めました。リスクマネジメントを行うためにはそのための土壌が大切で、プロマネはもちろん、その上司の方も目を通されてはと思います。
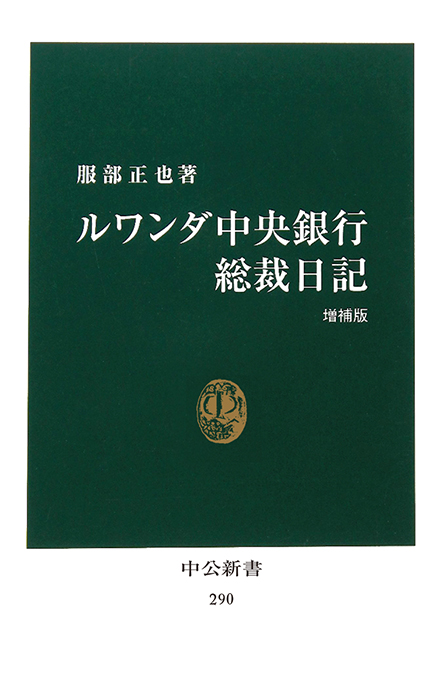
■『ルワンダ中央銀行総裁日記』服部 正也(中公新書)

三菱UFJアセットマネジメント 取締役社長
横川 直 SUNAO YOKOKAWA
1965年にアフリカ・ルワンダの中央銀行総裁に就任した、当時46歳の日本銀行出身者による奮闘の記録です。異文化・異環境のなかで、金融制度の構築に尽力した姿が克明に描かれています。どのような状況においても、最終的に信頼を築く鍵となるのは「人間性」であるということを気づかされる一冊です。困難な環境下でも諦めることなく、相手を尊重しながら成果を上げていく姿勢は、私達が日々取り組む業務にも通じると感じます。
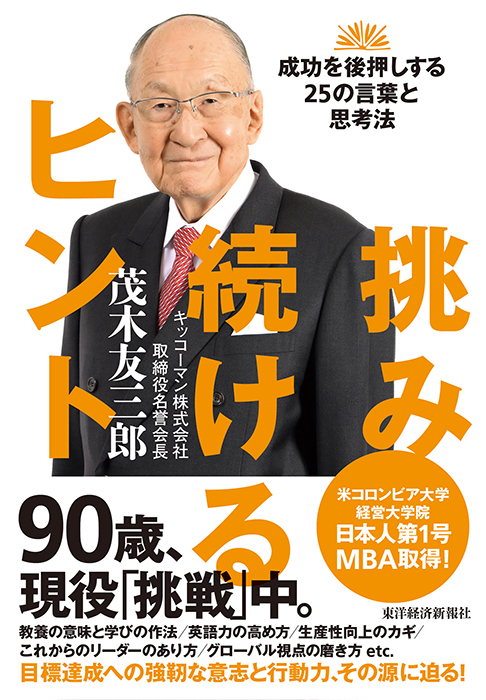
■『挑み続けるヒント 成功を後押しする25の言葉と思考法』茂木 友三郎(東洋経済新報社)

三菱UFJ信託銀行 取締役社長
窪田 博 HIROSHI KUBOTA
キッコーマン茂木名誉会長の最近の著書。1970年代の米国で醤油工場建設をゼロから立ち上げ、現在のグローバル企業への転換の礎を築いた経験から、グローバル展開へのチャレンジの重要性を会社の発展のみならず個人の成長機会の両面から記載。90歳でなお現役であり続け、そのさまざまな体験に基づく、分かりやすく、かつ心に響く数行での格言の記載も随所にあり、若手だけでなく経営者にも非常に有意義な一冊。
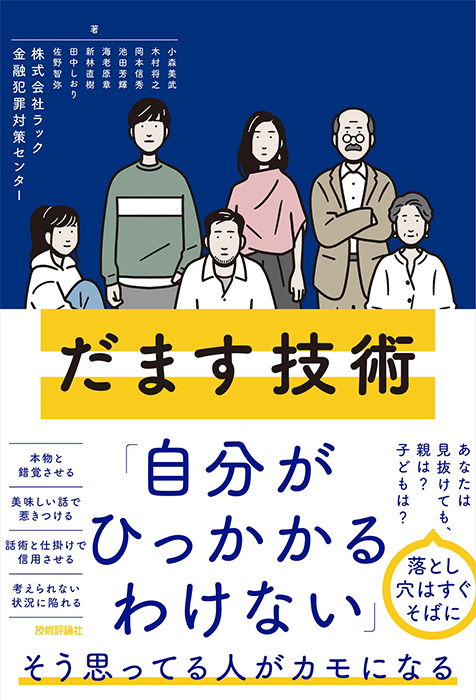
■『だます技術』ラック 金融犯罪対策センター 小森 美武、木村 将之、岡本 信秀、池田 芳輝、海老原 章、新林 直樹、田中 しおり、佐野 智弥(技術評論社)

三菱UFJニコス 代表取締役社長
角田 典彦 NORIHIKO SUMITA
金融詐欺犯罪に関わる名著で、題名の通り、多種多様な詐欺の技術が紹介され、具体的な手口が書かれている点が秀逸です。さらに「だまされる可能性を下げるには」という章では、詐欺にあわないために「やるべきこと」が詳しく列挙され、題名とは逆に「だまされない技術」も紹介されています。
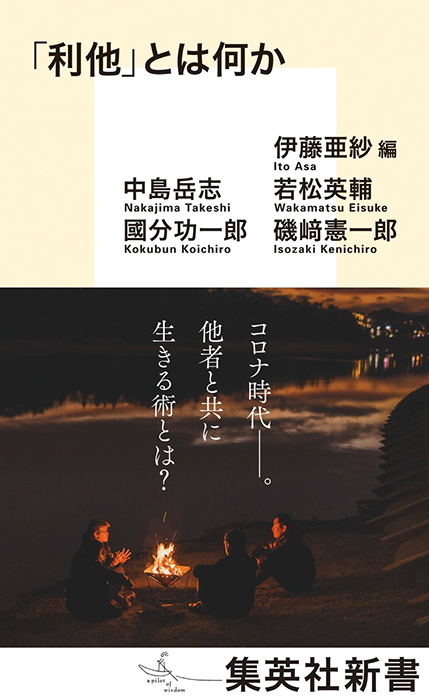
■『「利他」とは何か』伊藤 亜紗編著、中島 岳志、若松 英輔、國分 功一郎、磯崎 憲一郎(集英社新書)

明治安田生命保険相互会社 取締役 代表執行役社長
永島 英器 HIDEKI NAGASHIMA
格差・分断の拡大を背景に「利他」が注目されています。西欧の学者は「合理的利他」「功利主義的利他」を主張しますが、私達は損得で考える利他には違和感を覚えます。見返りを求めない、偶発性を伴う利他に心惹かれます。それは「主体的・能動的な人間観」と「縁起的現象としての人間観」の違いでもあり、能動態と受動態を明確にする英語のような言語は前者を背景にしています。会社経営と利他。私の最大関心事のひとつです。



