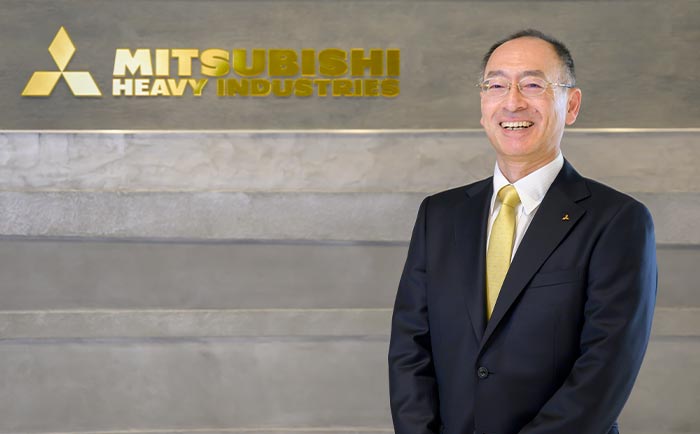三菱関連企業のトップのお考えやお人柄をお伝えする連載『トップインタビュー』。第29回は小岩井農牧社長の辰巳 俊之氏に小岩井農場の概要や歴史、キャリアの話、社長としての会社の目標などについて聞いた。

趣味は歩くこと。最近は奈良が好きで、時間があれば訪問して歩く。食べ物は何でも好きだが、とくに中華が好き。愛読書は稲盛 和夫氏の本。
小岩井農牧 代表取締役社長
辰巳 俊之(たつみ・としゆき)
1957年神奈川県生まれ。1981年日本大学農獣医学部卒業。同年小岩井農牧に入社。酪農事業、輸入業務、営業などを経て、2000年から経営開発室。2008年に取締役経営開発室長、2015年に常務取締役、2021年より現職。
経営企画を長く担当し、初の生え抜き社長に就任
2026年春、小岩井農場に富裕層向けホテルがオープン
――今夏、小岩井農場の来場者数はいかがでしたか。
辰巳おかげさまで7月、8月と好調でした。ただ、やはり国内のお客さまが多く、インバウンドの掘り起こしはこれからでしょうね。2024年は台湾や欧米からの訪問客の増加などにより、県内の外国人宿泊者数は38万人超と過去最多でした。これは2023年1月に米ニューヨーク・タイムズ紙の「2023年に行くべき52カ所」で盛岡市が選ばれた効果もあります。誘客拡大がこれから。県とも意見交換するなどして、新たな施策を練っているところです。

――岩手県の有力な観光資源でもある小岩井農場はどのように生まれたのですか。
辰巳小岩井農場は、1891年(明治24年)に、土佐藩出身で日本鉄道会社副社長の小野 義眞氏、三菱第二代社長の岩崎 彌之助氏、長州藩出身(長州ファイブの1人)で鉄道庁長官の井上 勝氏の3名が、東北地方への鉄道開通をきっかけに、殖産興業の一環として食料増産のため農牧事業を起こそうと開設した農場です。3人の名前から1文字ずつとって「小岩井」と名づけられました。
以来、2025年で134年。国内有数の農場に成長しました。宮沢 賢治は詩集『春と修羅』に「小岩井農場」というタイトルの長編詩を収めています。現在のような観光地となったのは昭和40年代。路線バスが走り、小岩井農場にピクニックに訪れる人達が増えたことで、農場に小さな牛乳売店をつくり、そこで皆さんがお弁当を食べるようになった。そうした流れから観光地として皆さんに親しまれるようになっていったのです。
――小岩井農場をはじめ、事業はすべて小岩井農牧が統括していますね。
辰巳小岩井農牧ではおもに5つの事業を行っています。それが酪農事業、山林事業、環境緑化事業、観光事業、食品事業です。小岩井農場は観光地として有名になり、食品事業は小岩井農場産を第一義に国内産にこだわり、低温殺菌牛乳・ナチュラルチーズなどの乳製品、チーズケーキなどの洋菓子を製造しています。小岩井乳業はもともと当社が1899年より開始した乳事業を、1976年にキリンビールと分離独立させた、合弁会社となります(現在はキリンホールディングスの直接子会社)。現在は農場内に乳業工場があることもあり、小岩井乳業とは密接に連携協調する友好関係にあります。

――社長が入社されたのはいつ頃ですか。
辰巳1981年です。牛飼いがしたくて、日本大学農獣医学部の農学科を卒業し、新卒入社しました。実家は横浜市内で商社勤めの家に育ちました。大学一年生のときに北海道に酪農実習に行きまして、これこそが自分の天職だと思ったのが入社を志したきっかけです。家族が力を合わせて仕事をするところに惹かれたのです。
新卒同期は14名。通常は4~5名ですが、その年は突出して多かったのです。しかし、私は入社1カ月で上司から「おまえは頭を冷やせ」と言われたんです 。というのも、入社後1カ月の研修期間中に現場を回るのですが、「こんな非生産的な会社があるのか」と感じ、研修発表会で社長を前に「この会社は腐っている!」と言ってしまったからです(笑)。

1980年頃、大学在学中に1年間休学して、米国ウイスコンシン州で1年間酪農実習をした際の辰巳社長
経営企画を長く担当し
初の生え抜き社長に就任
――結果、どうなったのですか。
辰巳すぐに葛巻町という県北の畜産公社に出向となり、2年ほどそこにいました。私も血気盛んだったのでしょう。当時の部長からは「もう帰ってくるな」と追い討ちをかけられました(笑)。しかし、結局は25歳で戻してくれました。それからは畜産公社を含めて10年ほど酪農の現場で働きました。そこで自分の本望通りの仕事ができました。その後、ドイツのメーカーとの提携事業の担当となり、食肉加工品の輸入業務、営業、商品企画を担当しました。ただ、社歴のなかでいちばん長いのは経営企画です。20年以上も務めました。
――経営企画を長く担当されたあと、2021年に初の生え抜きとして社長に就任されました。
辰巳生え抜き出身の強みは、現場を熟知していることかもしれません。就任後は現場力を上げていくと同時に、外からの視点や情報も積極的に取り入れていきたいと改革に取り組んできました。本社は東京にありますが、小岩井農場の方が滞在時間は長くなっていますね。
経営企画を長くやったこともあり、社外とのアライアンスも多く経験しています。私は会社にはケミストリーが必要だと考えています。伝統企業だからこそ、新たな化学反応を起こす革新が大事だと思っているのです。

――小岩井農牧は130年以上の歴史を誇る伝統企業ですが、これからの課題とは何ですか。
辰巳人材活用が大きな課題だと思っています。当社の社員は真面目で明るい。いかに若手の人材を活性化していくか。それが将来の会社の命運を決めると考えています。現在は、あらゆる現場で人手不足が深刻化しており、私達も例外ではありません。地元の岩手大学の畜産系の勉強会に参加したり、大学の先生との人脈を構築したりして、挑戦を厭わない新たな人材を発掘したいと思っています。
2026年春、小岩井農場に
富裕層向けホテルがオープン

――最近の動向で注目すべきことはありますか。
辰巳2026年春にホテルがオープンします。かねがね小岩井にホテルが欲しいと思っていましたが、足掛け15年ほどかけてやっと実現することになりました。JR東日本グループがアマングループの創業者で世界的ホテリエであるエイドリアン・ゼッカ氏と連携し、小岩井農場の地に富裕層向けホテル「AZUMA FARM KOIWAI」を開業します。小岩井農牧や地域の皆さまと連携したさまざまなアクティビティや、空飛ぶクルマなどのモビリティなどを通じて、新たな体験や地域の価値を創造していく予定です。
――今後も多くの来場者が小岩井農場に訪れると思いますが、農場でいちばん見てほしいと思っていらっしゃるところはどこですか。
辰巳小岩井農場に遺っている農業近代化遺産の佇まいですね。明治から昭和初期にかけて建設した建造物21棟を、国指定重要文化財「小岩井農場施設」として保存、活用しています。これらはオーナーであった岩崎 久彌さんの時代につくられたものばかりで、久彌さんの小岩井農場に対する思いや願いが反映されたものだといえます。現在は公益財団法人小岩井農場財団が管理しており、現在も稼働し続けている生きた文化財です。小岩井農場の歴史は、我が国の酪農をはじめとした畜産業の歴史であり、その生産工程・生産技術の試行錯誤・発展の歴史でもあります。一号牛舎、一号・二号サイロ、四階倉庫、本部事務所など、これらの歴史的建造物を国の宝とともに三菱の宝として修復・保全し後世に遺すことで、学術・文化の振興に寄与したいと考えています。
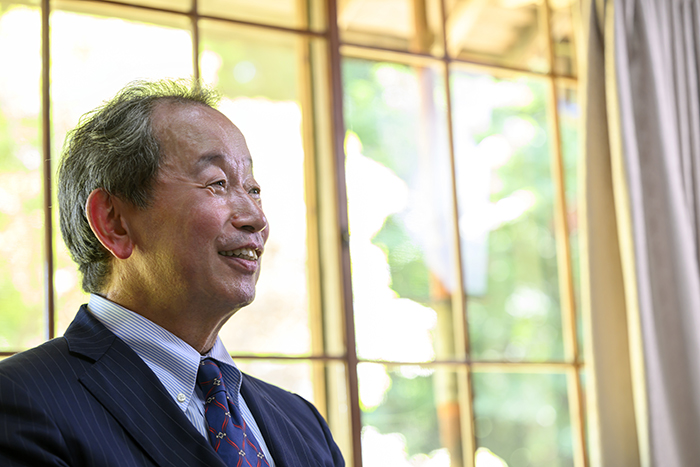
――最後に読者へのメッセージをお願いします。
辰巳まずは従業員が幸せになれるようにしていきたい。そのためには従業員の物心両面の幸せを実現できる農場にしていきたい。新たな展開として来年春にはホテルも稼働しますので、ぜひ久彌さんが愛し思いを馳せた小岩井農場にお越しいただければと思っています。