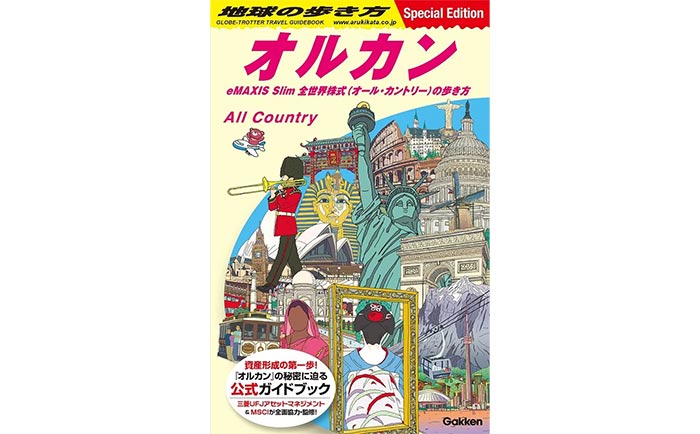2025年秋を目処に、三菱鉱石輸送が船舶管理システムを刷新する。親会社である日本郵船が開発した『NiBiKi』を導入。現在、新システムへの移行作業を進めている。
船の入港タイミングやクルーの休暇時に合わせ
新システムへの移行作業や教育を実施
「船舶管理業務の根幹である船舶管理システムと安全管理マニュアルを刷新するということは、当社にとって大きな決断でした」
安全・環境・品質保証グループ長 兼 技術支援チーム長の池田 康宏さんは、現在進めている『NiBiKi』導入をこのように表現する。
『NiBiKi』を導入することにした背景には、それまで使っていたシステムの老朽化に加え、日々高度化する業界の安全基準を満たす安全管理マニュアルを限られた人材でアップデートし続けることの難しさがあった。『NiBiKi』は船舶管理プラットフォームで、日本郵船グループ共通のSMS(Safety Management System)マニュアルや船上業務の申請ワークフローで構成。SMSマニュアルだけを活用することもできるが、プラットフォームとマニュアルの両方を『NiBiKi』でそろえていた方が移行しやすく日本郵船グループとしての協働もしやすいという判断などから両方をセットで使うことに決定し、2024年10月に導入が承認された。
新システム刷新で期待されるのが、業務の効率化だ。旧システムでは報告や申請をする際に、専用テンプレートに書き込んだものをメールで送っていたが、『NiBiKi』は船上業務の申請ワークフローのためのモジュールが実装されており、各種報告や船上整備作業の内容確認、本船への指示、承認が本船・船舶管理会社ともにシステム上で完結する。具体的には、本船はモジュールを介して、報告や船上整備作業に関する申請を提出。日本で本船を管理している担当者は担当船から報告や船上業務の申請が通知されるようになっており、システム上で対応することができる。上記により作業負荷を軽減し、タイムリーな対応が見込めるのだ。

『NiBiKi』導入イメージ。
現在、段階を踏んで移行作業を行っているところで、クルー向けの『NiBiKi』の使い方やSMSマニュアルの内容に関する説明会およびトレーニングを順次進めている。また、新システムで使うサーバー用のパソコンを、管理している全船に搭載する作業も行っている。
刷新後も船が支障なく安全運航でき、システムが問題なく稼働できると判断されるまでの間、旧システムも並行稼働させる。池田さんは新システムへの移行状況を次のように話す。
「パソコンを搭載するにしても全船に行き渡るのに2カ月近くかかります。相手は世界中を走っている船。入港する場所とタイミングを見計らって届ける必要があるため、なかなか時間のかかる話です。クルーへの教育も、講師を船に出張させて行うのは大変なので、休暇で船を降りてきたクルーを対象に順次実施しているところです。しばらくすると教育を終えた乗組員が一定数に達しますので、その時点で『NiBiKi』に完全移行すれば船が止まることもありません」
強みは船上勤務者と陸上勤務者の距離感の近さ
末端のクルーまでマニュアルの運用を徹底させる
『NiBiKi』と同時に導入される新SMSマニュアルについて池田さんは、「自社で作成・運用してきたSMSマニュアルと比較して大きく異なる点はありませんが、日本郵船グループ全体の経験やノウハウが随所に盛り込まれています」と印象を口にする。
社内では当初、『NiBiKi』のSMSマニュアルに切り替えることに対しては賛否両論があった。否定的な理由として、「マニュアルは我々の命、自主・独自路線を継続すべき」「NiBiKiに関して我々は後発組、先行するグループ会社と同じ土俵に立つと競争に勝てない」などといった声があがった。
しかし、『NiBiKi』導入はより大きな視点で進めるべきと判断した。当社の強みは、現場の船員と陸上勤務の人達との距離感の近さ。クルーと陸上勤務の管理担当の間で人事のローテーションを実施するなど、日本人社員、フィリピン人クルー、フィリピン人クルーを配乗する専属会社の幹部の多くは両者の立場を経験している。そうした環境から、クルーと陸上勤務者の連携が自然に取りやすいことを生かし、マニュアルの運用を末端まで徹底することにした。現場との距離感について池田さんは次のように話す。
「最初はSMSマニュアルに慣れていないため、他社と比べて不利になることは否めません。厳しい状態に置かれることは短期的には避けられませんが、だからといってこういう状況が5年も10年も続くとは思えません。陸上で勤務する私達のなかにはクルー経験者が多く、現役のクルーとの距離感が近いことから、末端のクルーまでSMSマニュアルを理解させることができ、しっかりと運用することで差をつけることができるはずです」
現場との距離感の近さは、SMSマニュアル運用を末端まで徹底させることだけではなく、親会社である日本郵船に現場の声を届けることにも生かせそうだという。
業界でいち早く『Starlink マリタイム』の導入を決定
陸上と同等レベルの通信速度を実現する
「以前から船で衛星通信サービスを利用していましたが、通信速度が陸上の1/60程度と遅く、メールを1通送るにもだいぶ時間がかかっていました。画像などを添付する際も、データが最大2MBまでと制限がかかっており、大きなデータを送る場合は何回かに分けて送らなければならないなど不便なところがありました」
また、クルーがプライベートで自由に使える携帯電話の通信データ容量が月2GBしかなく、家族などとのコミュニケーションは音声通話やチャットに限られた。そのため、通信速度の遅さや、使えるデータ容量の少なさに対するクルーの不満はかねてから大きかった。

本船に設置されたStarlinkアンテナ。
そこでこの問題を解決するために『Starlink マリタイム』を導入することにし、『Starlink マリタイム』が日本でも購入できるようになったことを受け、業界に先がけていち早く導入することを社内で提案。しかし、乗船時に家族などとのコミュニケーションが取りづらくなる環境を当たり前のものとして経験してきた上層部から、「必要か?」と反応され、当初はなかなか理解が得られなかった。船員の福利厚生面だけではなくビジネス利用の面でも、「安定して使えるのか?」「バックアップは大丈夫なのか?」と心配された。最終的には、これまで使っていた衛星通信サービスよりもかなり格安に利用できることや、初期費用として必要なアンテナ購入費が安いことに加え、既存の通信サービスのコスト最適化を図ったプランへ移行したうえで、従来の通信システムをバックアップ回線として継続的に運用できるようにすることなどを提案・訴求し、導入の理解を得ることができた。
『Starlink マリタイム』導入後は、海上でも陸上と同等のスピードでの通信を実現。メールに添付できるデータの制限もなくなった。何か問題が発生したときも、船長と機関長に持たせているiPhoneからFacetimeによるビデオ通話や、ショートメッセージによる画像のやりとりなど、遅延の少ないリアルタイムなコミュニケーションが可能になったことで、管理担当から迅速かつ的確な指示を受けて対処できるようになり、情報共有の質と効率が飛躍的に向上した。
クルーの福利厚生で割り当てられている携帯電話の通信データ容量も2024年9月から10GBと大幅に拡大。家族などとのビデオ通話はもちろん、動画のサブスクリプションサービスの船上での利用も可能になった。
小故島さんは「10GB使えるようになったことは、クルーから好評で、とても喜ばれています」と話す一方、10GBの支給方法はひと工夫した。
「従来の衛星通信サービスのときは、2GBを使いきってしまったクルーから追加で通信データ容量が欲しいと頼まれることがありました。この経験から、一度に1カ月分である10GBを渡してしまうと、月末までに使い切ってしまい追加分を要求される可能性が考えられたことから、計画的な利用を促すために週単位での支給としました。週に2GB、3GB、2GB、3GBと分けて支給をすることで、トータルで10GBを渡すかたちです」
業界としてもクルーの福利厚生は関心が高い。離れている家族などとコミュニケーションを取れる環境を会社が整えることは、クルーが船上で生き生きと仕事をしてもらうために大切なことだ。安全管理マニュアルと同様に、力を注ぎたいところだ。
INTERVIEWEES

池田 康宏 YASUHIRO IKEDA
安全・環境・品質保証グループ長 兼
技術支援チーム長

小故島 汐里 SHIORI OKOJIMA
安全・環境・品質保証グループ
技術支援チーム
三菱鉱石輸送株式会社
チリ国アタカマ鉄鉱石を八幡製鉄(現日本製鉄)向けに輸送するため、三菱商事、三菱鉱業(現三菱マテリアル)などの共同出資により、1959年に設立された。1964年より現社名に変更。船主業、船舶管理業を軸に、ばら積み船ほか、自動車専用船など計14隻を展開する。資本金15億円、従業員数42名(日本人海技者を含む、2025年4月1日現在)。2023年4月に日本郵船の完全子会社となる。